タイの家計事情で面白い記事を見つけました。タイの銀行「ttb」が行った調査によるとタイのサラリーマンの82%が借金を抱え、月収10万バーツ(約40万円)以上でも貯金ができない人が多いことが分かりました。収入は増えても支出が追いつき「月末にはお金が残らない」という声が現地では珍しくありません。その背景には親や兄弟を支える“เดอะแบก(デオバッグ)文化”と呼ばれる家族中心の価値観が根付いています。今回はタイ人の家計事情を通して見える「お金」「幸せ」「消費行動」のリアルを紐解きながら、日本企業がタイ市場で成功するためのヒントを探ります。
出典:Brand Inside(2025年10月29日)
「มนุษย์เงินเดือนไทย ถึงจะรายได้เป็นแสน แต่ใช้จ่ายเดือนชนเดือน เพราะเป็น ‘เดอะแบก’ ของครอบครัว」
https://brandinside.asia/ttb-financial-thai-salary-man-health-check/
82%が借金を抱える?TTB調査で見えた“現実”
「Financial Health Check」の調査概要
タイの銀行「ttb financial group」による調査「Financial Health Check」では、タイのサラリーマンの約82%が何らかの借金を抱えているという結果が明らかになりました(出典:Brand Inside)。この調査はタイ国内の給与所得者を対象に収入・支出・負債の状況を分析したものです。負債の内訳を見るとクレジットカードや個人ローンが最も多く53%、次いで車のローンが17%、住宅ローンが15%と続きます。こうした数字からタイの中間層が拡大する一方で家計の健全性は依然として脆弱であることが読み取れます。
タイ人サラリーマンの収支バランス
調査によると給与が増えても支出が比例して増える傾向があり、貯蓄率の低さが課題となっています。実際77%の人が「収入の10%未満しか貯金していない」と回答し、約70%が「半年分の生活費に相当する貯蓄を持っていない」と答えています。医療や老後への備えが不十分な層も多く、金融リテラシーの低さや家計を支える多重責任構造が影響していると考えられます。
月収10万バーツ層でも「月末カツカツ」な理由
興味深いのは、月収10万バーツ(約40万円)以上の高収入層でも3割以上が「月末にはお金が残らない」と答えている点です。高収入であっても親への仕送り、子どもの教育費、住宅ローン、車の維持費など、家族を支える支出が重なります。タイでは家族を経済的に支えることが「責任」とされる文化が根強く、社会的にも“เดอะแบก(デオバッグ)=家族の背負い手”として尊敬されます。結果として個人の可処分所得は限られ、貯蓄が難しくなります。こうした家計構造を理解することはタイ市場で製品やサービスを販売するうえで欠かせません。数字だけでなく「家族を中心にしたお金の使い方」を把握することがタイ人消費者の心理を読み解く第一歩です。私自身、現地で営業活動を行っていた際も知り合いのタイ人や顧客やパートナー企業の担当者が「毎月のローン返済と仕送りで手いっぱい」と語る場面を多く目にしました。タイ人の親自身が子どもの仕送りをあてにしており、子どもはとても苦しい立場です。
なぜ“高収入”でもお金が貯まらないのか?
家族を支える“เดอะแบก文化”とは?
タイでは「เดอะแบก(デオバッグ)」という言葉があります。直訳すると“背負う人”という意味で家族の生活を支える中心的な存在を指します。Brand Insideによると高収入層ほど家族への仕送りや支援を積極的に行う傾向があり、収入の多くが親や兄弟の生活費、子どもの教育費などに使われています。これは単なる経済的負担ではなく「家族を支えることが誇りであり、愛情の表現」という文化的価値観に基づいています。私が商社勤務時代に見てきたタイの取引先でも、長男・長女が家族全員の生活を支えるケースが多く、これがタイ社会の根底にある“家族中心主義”を象徴していました。
教育費・住宅ローン・親の仕送りが重なる構造
タイの都市部では子どもの教育費が家計を圧迫する大きな要因です。私立学校や塾の費用が高額でバンコクでは中間層でも教育への投資意識が強く「良い教育が家族の誇り」と考えられています。マイホーム志向も高く、住宅ローンや車のローンが同時に発生することも珍しくありません。親への仕送りが重なり、たとえ月収10万バーツ以上の高収入であっても実際に自由に使えるお金は限られます。こうした複合的な支出構造が貯蓄を難しくしているのです。
日本との価値観の違い:「個人」より「家族」
日本では「自立」や「個人の生活の充実」が重視される傾向にありますが、タイでは「家族の幸せ=自分の幸せ」という価値観が主流です。家族を経済的に支えることは社会的信頼や尊敬を得る行為とされます。“家族に仕送りする=自己実現”という考え方です。この背景を理解せずに「タイ人は貯金ができない」と見るのは誤りです。タイ市場でビジネスを展開する際には、こうした価値観を踏まえ、家族で楽しめる商品や「共有」をテーマにしたマーケティング戦略が効果的です。タイの消費行動を理解する第一歩は家計の背後にある“家族の絆”を知ることから始まります。
借金への心理的ハードルが低いタイ人の金銭感覚
タイでは借金に対する心理的な抵抗が日本よりもはるかに低い傾向があります。私が現地で働いていた頃も街中に消費者金融の看板が並び、銀行からの営業電話も頻繁にかかってきました。私は優良物件なようで、それはもう色々なところから電話がきました。ローンやクレジットを活用することは“悪いこと”ではなく「必要なときにお金を動かす手段」として広く受け入れられています。
Brand Insideの調査でもサラリーマンの82%が借金を抱えているとされていますが、これは単なる経済的困窮ではなく“キャッシュフローの拡張”という意識が背景にあります。タイでは友人同士でも簡単に貸し借りが行われ、社会全体が「回していく」文化を持っています。支出が多くてもストレスを感じにくく、むしろ「今を楽しむ」行動を支える仕組みとしてローンを活用しているのです。
こうした価値観は、タイ人の購買行動にも直結しています。「少し背伸びしても、心が満たされる買い物をする」――それが多くのタイ人にとって自然な選択です。日本企業がタイ市場で成功するには、この“借金を前向きに捉える文化”を理解し、分割払い・プロモーションキャンペーンなど、心理的ハードルの低い販売設計を行うことが鍵になります。
借金があっても笑顔?“今を楽しむ”タイ人の幸福観
SNSで幸せを共有する文化
タイでは「今この瞬間を楽しむ」ことが幸福の源と考えられています。Brand Insideによると借金を抱える人が多い一方でSNS上では明るく充実した日常を発信する傾向が強いといいます。FacebookやInstagramは利用率が高く、食事・旅行・家族の笑顔を共有することが“幸せの証”として定着しています。私が現地で感じたのは投稿することで周囲とポジティブな感情を共有し、ストレスを軽減しているという点です。タイ人にとってSNSは自己表現の場であると同時に前向きな生き方を支える大切なツールなのです。
カフェ・旅行・プレゼント消費の心理
タイ人は「体験」にお金を使うことを好みます。カフェ文化は盛んで映える内装やスイーツを求めて週末には多くの若者が出かけます。私がタイで仕事をしていた頃も同僚たちは「新しいカフェに行くことが楽しい」と語っていました。旅行や誕生日プレゼントなど心を豊かにする支出には惜しみません。こうした傾向は他人との関係性を大切にする文化と深く結びついており「大切な人と良い時間を過ごす」ことが消費の原動力になっています。
「節約よりも心の満足」が優先される理由
日本では「貯金」や「節約」が美徳とされますが、タイでは「幸せを感じる瞬間を逃さない」ことが価値とされています。借金があっても日々の小さな喜びに投資することをためらいません。これは経済的な無計画さではなく、社会全体が「心の充足」を重視しているためです。タイ市場で商品やサービスを展開する際はこの“心の満足”を理解することが重要です。合理性よりも感情に寄り添うマーケティングがタイ人消費者の心を動かす鍵となります。
タイ人の消費行動から見える日本ブランドのチャンス
「実用性」より「感情で動く」購買パターン
タイ人の購買行動の特徴は「論理」よりも「感情」に基づいている点です。Brand Insideによると、タイの消費者は収入に対して支出の割合が高く、節約よりも「自分や家族の満足感」を優先する傾向があります。商品を選ぶ際に「必要だから買う」ではなく「気持ちが上がるから買う」ケースが多いです。私がタイ市場で商談を重ねてきた経験からも機能的な価値だけを訴求するより「どんな気持ちを得られるか」を明確に伝える方が反応が良いと感じます。日本ブランドがタイで成功するにはスペックよりも“感情の共鳴”を重視したアプローチが欠かせません。
“映える・共感できる”がブランド選びの鍵
SNSの普及によりタイでは「シェアしたくなる体験」が購買を左右しています。カフェや雑貨店でも“映える”デザインやストーリー性がある商品が人気です。タイ人は口コミやレビューを重視し「共感できるブランド」に強い親近感を抱きます。日本製品でも単に「高品質」だけでなく「かわいい」「ユニーク」「日本らしい世界観」など、SNSで話題化しやすい要素を持つブランドが支持されやすいのです。日本企業がタイ人の“シェアしたくなる心理”を理解すればSNSを通じて自然な拡散を生み出すことができます。
日本企業がタイ市場で意識すべき3つのポイント
第一に製品の「感情的価値」を伝えること。使うことで得られる楽しさや誇らしさを打ち出すと効果的です。
第二に「共感」を育てるブランドストーリーを構築すること。創業背景や職人の想いなど、日本的な“誠実さ”を語ることで信頼を得られます。
第三に「SNSと連動した体験型プロモーション」を意識すること。実際に試せる・写真を撮りたくなる仕掛けは、現地消費者の行動を動かします。
タイ市場では“心を動かすブランド”こそが生き残る鍵です。
まとめ|数字の裏にある「タイの豊かさ」
TTBの調査によるとタイのサラリーマンの多くが借金を抱え、貯金も十分ではありません。その背景には「家族を支えることが誇り」「今を楽しむことが幸せ」という価値観が深く根付いています。私がタイに住んでいた18年間で感じたのは、経済的な数字だけでは測れない“心の豊かさ”があるということです。街中には消費者金融の看板が立ち並び、銀行からの営業電話も頻繁にかかってきますが、タイ人は借金を「悪」とは捉えず、生活を前向きに回す手段として受け入れています。これは日本のような「節約・貯蓄中心」の価値観とは対照的です。
タイ市場で成功するためには、こうした生活のリアルを正しく理解することが欠かせません。数字だけを見れば「消費余力が少ない市場」と見えるかもしれませんが、実際には“感情で動く購買層”が確かに存在します。家族や友人と過ごす時間を大切にし、心を満たすものにお金を使う——その文化を踏まえたマーケティングや商品開発こそがタイ人の共感を得る鍵です。事実、日本をに訪れるタイ人は日本では思いっきり消費します。私の経験上、日本企業がタイで成果を上げるためには「ロジック」ではなく「共感と体験」で伝える姿勢が求められます。タイ人の幸福観を理解し、現地に寄り添うこと。それが持続的な信頼とビジネス成功への第一歩です。
タイ進出を考えてる方はお気軽にお問い合わせください。


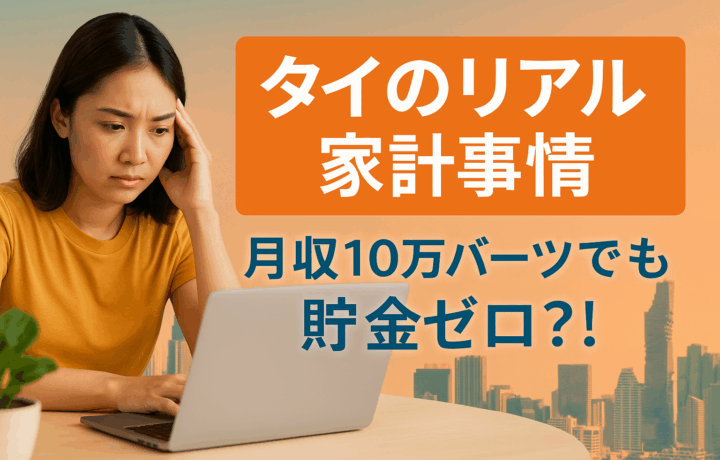
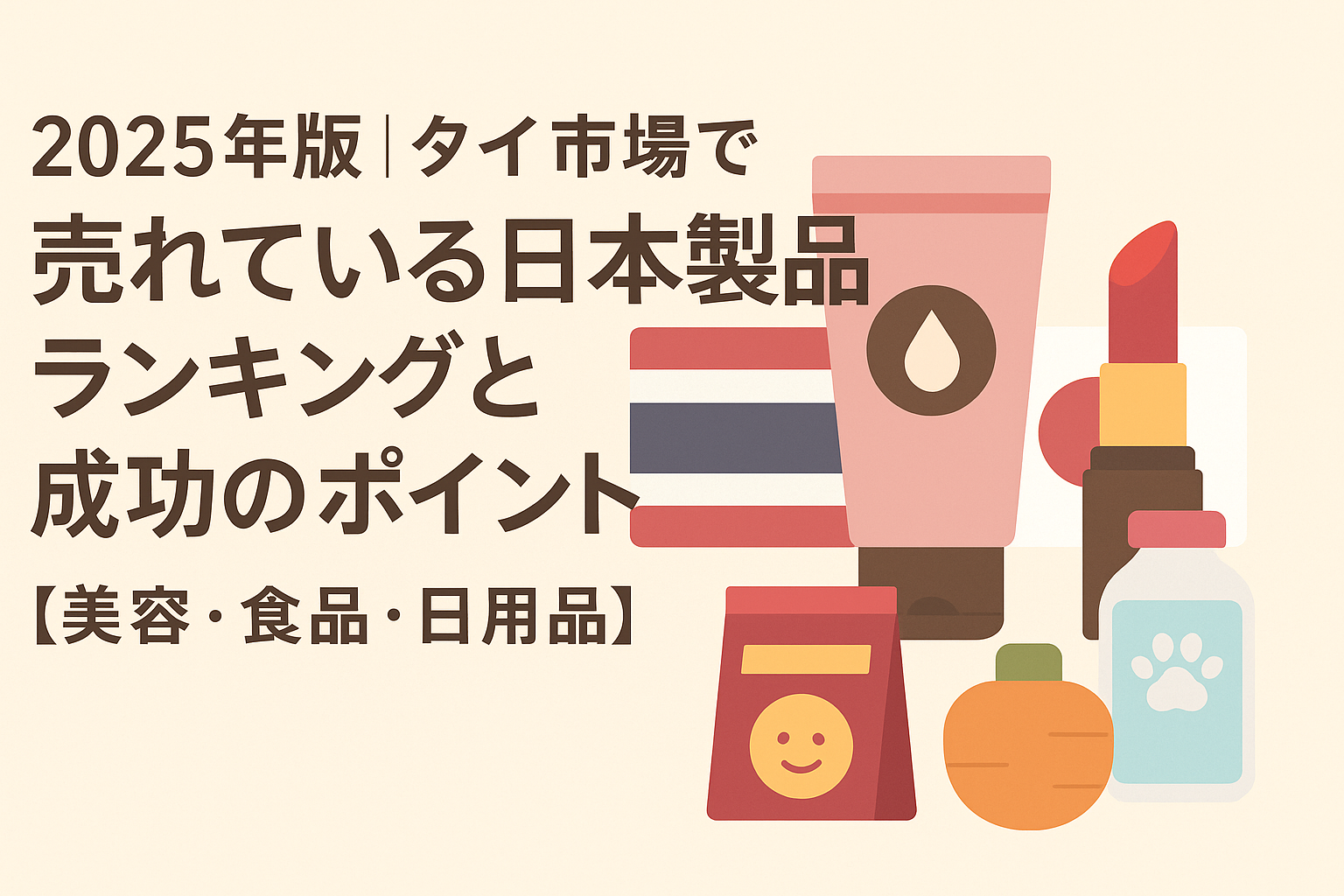

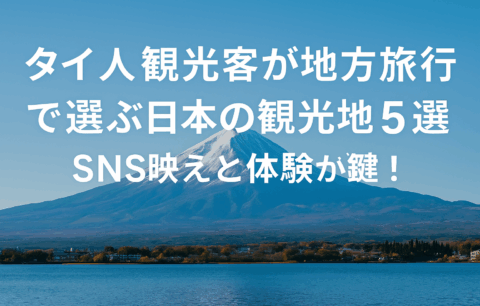



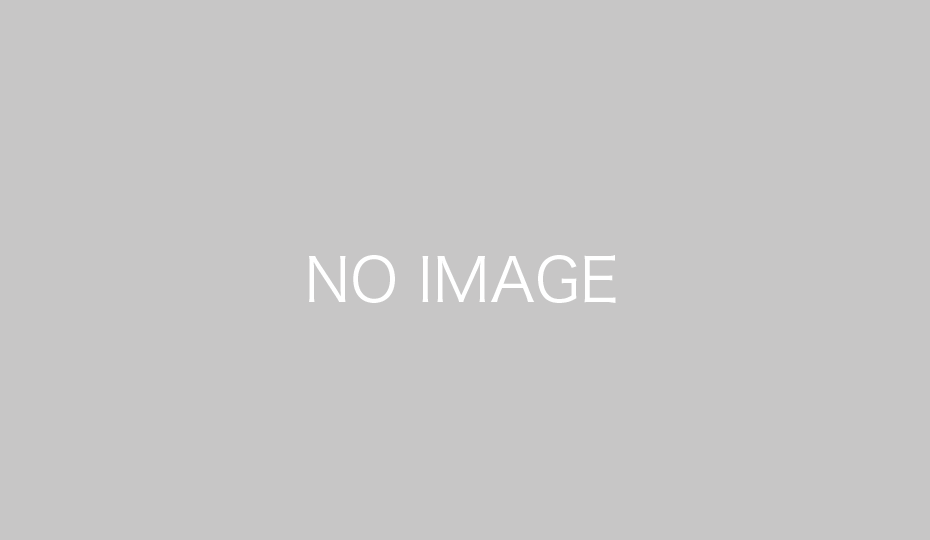



コメント