観光大国として世界に名を馳せたタイ。しかし、ここ数年でその勢いに陰りが見え始めています。かつて「アジアの観光成功モデル」とされたタイは、現在、主要都市でも観光客が減少し、地方観光地の成長も鈍化。観光地のマンネリ化、物価上昇、交通アクセスの不便さなど、構造的な課題が表面化しています。タイPBSによると、国内観光も減少傾向にあり、観光の“黄金期”は終焉を迎えつつあります。これは決して他国の話ではなく、日本も同じ課題を抱えています。本記事では観光大国タイの現状から、これからの日本が目指すべき「持続可能な観光戦略」を考えます。
現地のメディアであるタイPBSの記事を参考に解説します。
https://policywatch.thaipbs.or.th/article/economy-196
タイ観光が「黄金期」を終えた理由
主要都市でも観光客が減少、地方観光地も伸び悩み<
タイPBSの経済分析によると、観光大国タイが誇った黄金期はすでに終わりを迎えつつあります。かつて年間4,000万人を超える外国人観光客を受け入れたバンコクやチェンマイなどの主要都市では、観光客の伸びが鈍化。地方都市も同様で、かつて「次の人気エリア」とされたチャチュンサオやチャンタブリー、トランなどでも、観光客数が前年比マイナスに転じています。観光業界の専門家によると、パンデミック後の反動需要はすでに一巡し、各都市が「成長の限界」を迎えていると指摘されています。
既存観光地の「体験のマンネリ化」
観光地が抱える最大の課題は「新しさの欠如」です。多くの観光地では以前と同じアクティビティやツアー構成が続き、リピーターにとっての“新鮮味”が失われています。外国人観光客の間では「一度行けば十分」という声が増え、リピート率が低下。TTB analyticsのレポートでも、観光地の“体験の更新”が進まなければ、長期的な成長は難しいと警告しています。これはタイだけでなく、日本の地方観光にも共通する課題です。観光資源の「再編集」と「物語化」が、今後の成長を左右するでしょう。
国内旅行者も減少傾向――旅行が“特別な行為”に戻る<
さらに深刻なのが、タイ人自身の旅行離れです。TTB analyticsの分析では、経済不安と生活コスト上昇により、国内旅行の回数が減少。かつて気軽に出かけていた「週末旅行」が減り、旅行は再び“特別な行為”へと逆戻りしています。これは観光の「日常化」が崩れつつあるサインです。観光を支えるのは外国人だけでなく、国内需要の安定的な循環でもあります。持続可能な観光を実現するには、地元住民が誇りを持って再訪するような「地域再体験型の観光設計」が必要です。
観光産業を苦しめる経済・交通インフラの課題
物価上昇と所得格差――“旅のコスパ”が悪化
観光大国タイの失速を語るうえで、避けて通れないのが「経済格差の拡大」と「物価上昇」です。TTB analyticsの分析によると、タイ国内では燃料費や宿泊費の高騰により、観光コストが上昇。中間層・地方在住者にとっては、旅行が“贅沢品”へと逆戻りしています。かつては「気軽な週末旅行」が可能だった層が、今では生活費を優先する傾向が強まり、国内観光の動きが鈍化しています。 観光地の物価上昇が「費用対効果(コスパ)」の悪化を招き、旅行先としての魅力を下げる結果に。これは外国人観光客にも共通しており、為替や宿泊単価の上昇によって「タイが以前ほど安くない」と感じる声も増えています。
交通アクセス問題(ラストマイルの壁)
タイ観光の課題のひとつに、「目的地までのアクセスの悪さ」があります。主要都市間は整備が進んでいるものの、観光の要である地方部では、空港から観光地までの“最後の一歩(ラストマイル)”が非常に不便です。公共交通が乏しいため、レンタカーやタクシーに頼らざるを得ず、移動コストが膨らむ一方で、外国人旅行者にはハードルが高い仕組みとなっています。これが地方観光の発展を妨げる大きな要因です。筆者が地方に出張に行った際、レンタカーを予約します。地方はタクシーがないです。また、レンタカーの台数も少ないので最低2週間前から予約しないと確保できませんでした。
公共交通網の未整備が地方観光を阻む
タイ政府は高速鉄道や新空港など大規模インフラ整備を進めていますが、依然として地方の観光地への“つながり”は限定的です。PolicyWatch(Thai PBS)も、「観光地間の交通ネットワークが不十分で、移動時間とコストが旅行意欲を削いでいる」と指摘。観光の拡大には、交通インフラの整備だけでなく、“地域間の連携”が不可欠です。 日本も同様に、地方空港や鉄道が十分に観光動線と結びついていない地域が多く、同じ課題を抱えています。観光の多様化と地域間連携は、訪日インバウンド戦略でも重要なテーマです。
変化する観光ニーズに追いつけないタイの現状
SNS時代の“体験重視”に対応しきれない施設構造
かつてのタイ観光は「安くて楽しい、写真映えする国」として人気を博しました。しかし、SNSを中心とした“体験重視”の旅行トレンドに、既存の観光施設が追いつけていません。PolicyWatch(Thai PBS)によると、観光地の多くが従来型の観光モデルに依存しており、訪問客が求める「新しい体験」や「物語性」に欠けていると指摘されています。「行く場所」から「感じる場所」への転換が進まなければ、リピーター離れが進む一方なのです。これは日本の地方観光にも共通する課題であり、体験設計やブランドストーリーの構築が今後の鍵となります。
All-Season Tourism(通年型観光)への転換が急務
タイ観光のもう一つの構造的課題は、シーズン依存の高さです。乾季(11月~2月)に観光需要が集中し、雨季は「閑散期」として観光業全体が停滞します。TTB analyticsの分析でも、地域ごとの稼働率格差が広がり、観光関連雇用の不安定さを生み出していると指摘されています。近年は「Green Season(雨季の魅力)」という新しいプロモーションも進みつつありますが、まだ十分に浸透していません。日本でもオフシーズン観光の課題は同じで、年間を通じて地域経済を循環させる仕組みづくりが求められています。
観光ブランディングの再構築――「雨季=マイナス」の発想転換
観光地の“季節イメージ”を変えるには、マーケティングの再設計が必要です。タイPBSの提言でも「雨季=マイナス」ではなく「自然と一体になれる季節」として再定義すべきだと強調されています。雨季特有の森や滝の美しさを活かしたエコツーリズムや雨をテーマにしたカフェ・スパ体験など“気候を楽しむ”観光開発が今後の鍵になります。これは訪日インバウンドにも通じる考え方で、気候・地域性を生かしたストーリーデザインがブランド力を高めます。
タイの課題は“日本の明日”
地方観光の飽和、リピーター離れは日本も同じ構造
タイで見られる観光低迷の背景には「地方観光の飽和」と「リピーター離れ」という二つの構造的課題があります。TTB analyticsのデータによると、観光都市として成長してきた地方都市でも、近年は伸び率が鈍化。かつて“穴場”だった県も観光地化が進み、訪問体験が似通ってきたことで、旅行者の再訪意欲が下がっていると指摘されています。 これはまさに日本の地方観光が直面している課題と同じです。どの地域も「自然・食・温泉」という同じ切り口で発信しており、体験価値の差別化が難しくなっています。リピーターを生み出すには、「再訪したくなる理由」を地域ごとに設計する必要があるのです。
新しい体験を生む“地域の創造力”が鍵
観光の停滞を打破するには、“地域の創造力”が欠かせません。PolicyWatch(Thai PBS)は、タイの観光地が成長の鈍化に陥った理由として、「新しい体験を生み出す仕組みの欠如」を挙げています。単なる観光資源の紹介ではなく、地域住民やクリエイターが関わる“共創型の体験設計”こそが、旅行者の感情を動かす要素です。日本でも、地域の個性や文化を生かした観光リブランディングが求められています。
観光を「消費」から「共創」に変える時代へ
観光の本質はモノや景色を“消費する”ことから、“共に作る”方向へシフトしています。タイの事例は観光が単なる経済活動ではなく、文化交流や地域共創のプラットフォームであることを示しています。日本も同じ転換期にあります。観光客を“お客様”として扱うのではなく、“地域の共演者”として迎え入れる仕組みをどう構築するかが、今後の成長を左右するでしょう。
まとめ
観光大国タイが直面しているのは一過性のブームに頼った観光モデルの限界です。今後は“数”ではなく“質”、そして“リピーター”を中心とした観光設計が求められます。地域の文化やストーリーを掘り下げ、旅行者が何度でも訪れたくなる仕組みを整えることこそ、観光立国の持続性を支える鍵です。雨季を「グリーンシーズン」として再ブランディングしたように季節の多様性を観光資源に変える発想が重要です。日本も四季それぞれの魅力を再編集し、季節に縛られない体験型コンテンツを生み出すことで観光需要の平準化が可能になります。これこそが地域経済の安定化と雇用維持につながる“サステナブルな観光戦略”です。
WITHTHAIでは、タイ市場を中心にSNS運用・KOL施策・現地調査などを通じて、観光地や自治体の“本当に届く”プロモーションを支援しています。 タイ人観光客は、感情に響くストーリー性とリアルな体験共有を重視する傾向があり、日本の地域観光との親和性が高い市場です。
インバウンド戦略を見直したい自治体・企業の皆さまへ――
タイ人観光客向けSNSマーケティングや現地プロモーションのご相談は、WITHTHAIへ。
👉 関連記事:








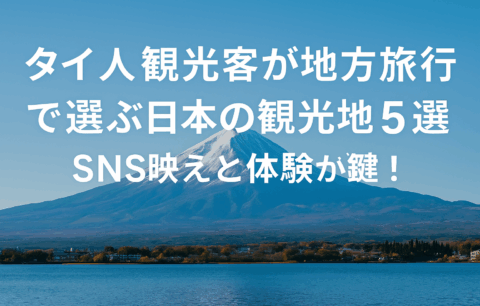
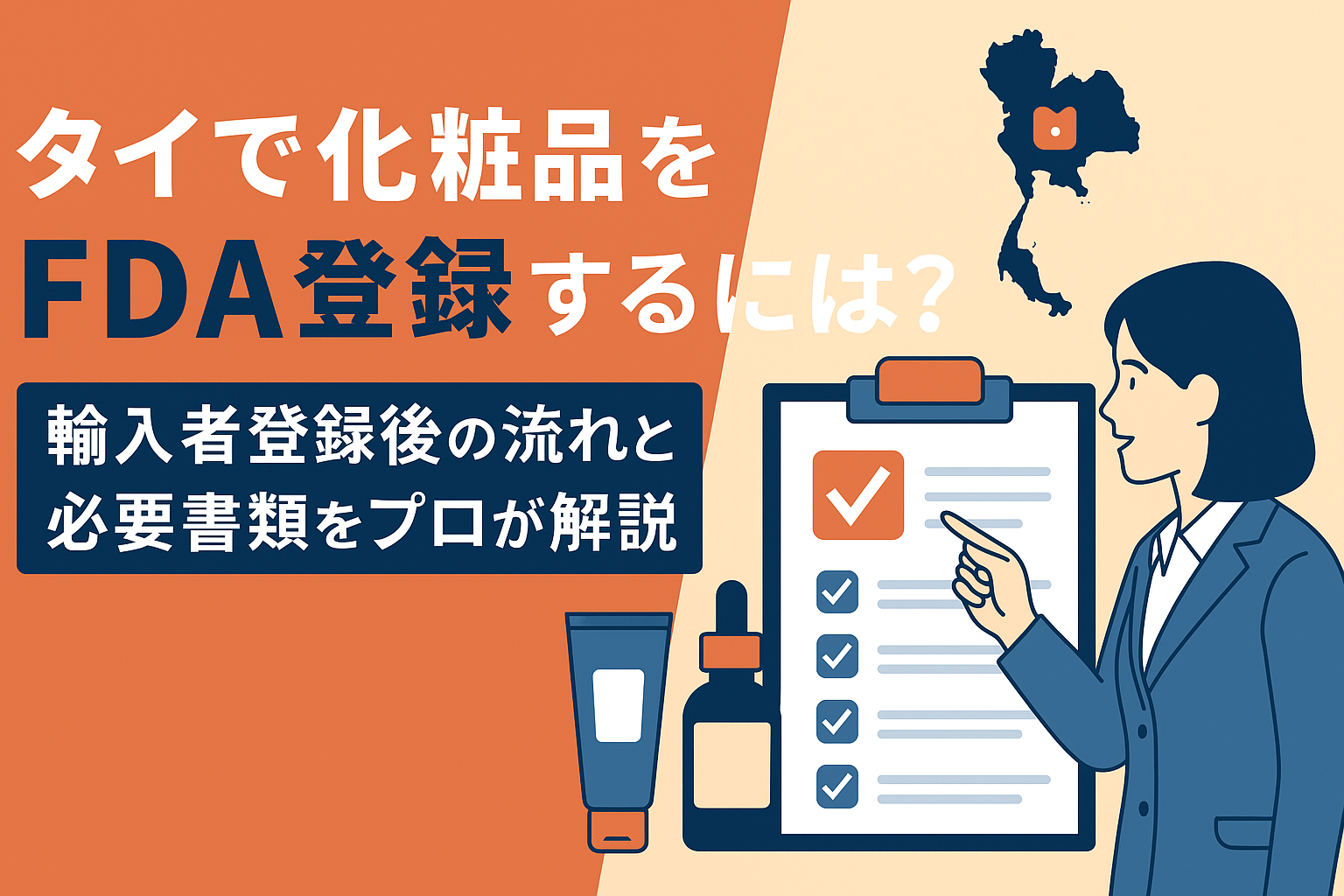
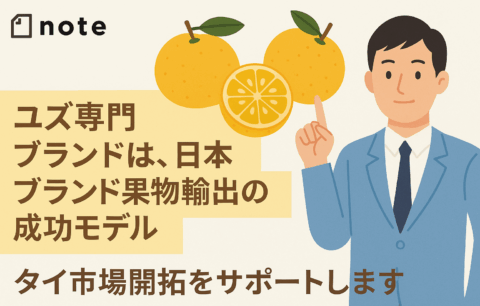



コメント