観光大国として世界中から注目を集めてきたタイ。しかし、2025年の今、その勢いに陰りが見え始めています。長年インバウンドを支えてきた中国人観光客が激減し、ホテルの稼働率は落ち込み、観光都市チェンマイでは閉業が相次いでいます。背景には誘拐事件や地震などによる治安不安、そしてバーツ高による「割高感」があります。観光収入がGDPの約2割を占めるタイにとって、この減速は国家経済そのものを揺るがす事態です。いまタイで起きていることは、決して他人事ではありません。――日本のインバウンドもまた、中国人観光客への過度な依存という“同じ構造”を抱えているのです。
日経ビジネスの記事を参考に解説していきます。
観光大国タイが直面する現実
中国人団体客が戻らないチェンマイの現場
タイの人気観光地・チェンマイでは、これまで観光バスであふれていた旧市街や寺院前の通りが、今では静けさを取り戻しています。日経ビジネスの記事によると中国人俳優の誘拐事件以降、中国人旅行者のタイ離れが加速し、国慶節シーズンでさえ例年のにぎわいは見られませんでした。筆者も在タイ時代、国慶節や春節の時期にホテルやレストランが予約で埋まる光景を何度も目にしましたが、現在はその姿が一変しています。観光バスの減少は単なる一時的な減速ではなく、観光産業が中国依存から抜け出せない構造的な課題を映し出しています。
稼働率70%止まり――ホテル業界の悲鳴
タイ北部ホテル協会によれば、2025年の国慶節期間中、高級ホテルの稼働率は85%前後、中級ホテルでは70%にとどまりました。前年はほぼ満室に近い稼働率だったことを考えると、落ち込みの深刻さがうかがえます。チェンマイでは、観光シーズン前からキャンセルが相次ぎ、客室単価の値下げを余儀なくされるホテルも増えています。団体旅行に依存していた宿泊施設は、個人旅行客への対応やマーケティングが追いつかず、集客モデルの転換が急務です。
閉業ラッシュが象徴する“依存の終焉”
日経ビジネスの記事では、チェンマイだけで少なくとも10軒以上の中国人向けホテルが閉業したと伝えています。多くの施設が中国旅行代理店との契約に依存していたため、顧客層の変化に対応できませんでした。特定の国への過度な依存は、突発的な地政学リスクや為替変動の影響を一気に受けてしまう――それは日本のインバウンドにも共通する教訓といえるでしょう。
中国人観光客が離れた3つの要因
治安不安(俳優誘拐事件・地震・軍事衝突・銃撃事件)
日経ビジネスの記事によるとタイ観光の失速には「治安不安の連鎖」が大きく影響しています。2025年1月に発生した中国人俳優の誘拐事件を皮切りに、ミャンマー地震やカンボジアとの国境衝突など、タイ周辺で不安定なニュースが相次ぎました。それ以前に中国人観光客が離れる事件が、2023年10月にバンコク中心部の高級商業施設「サイアム・パラゴン」で起きた銃撃事件です。タイ人未成年が発砲し、中国人観光客が死亡するという痛ましい事件は、中国のSNS上で瞬く間に拡散されました。筆者も当時バンコクに滞在していましたが、事件直後から観光地にいた中国人団体が一気に姿を消したのを覚えています。治安の印象が崩れると、たとえ一時的な事件でも回復には時間がかかります。家族連れや女性客を中心に「タイは危険」という認識が定着してしまい、ここから中国人観光客離れが本格的に始まりました。
通貨高による「割高感」
もう一つの要因は、バーツ高による旅行コストの上昇です。日経ビジネスによれば、人民元に対してバーツが上昇したことで、同じ予算でも日本やベトナムの方が“コスパが良い”と感じる旅行者が増えました。観光業が一国の顧客層に偏ると、こうした為替変動の影響を直接受けやすくなります。筆者も商社勤務時代に為替リスクの重要性を痛感しましたが、観光産業も例外ではありません。価格に敏感な層ほど他国へ流れやすく、団体ツアー客の動向は顕著です。
SNS時代のネガティブ拡散
SNSが情報の流れを劇的に変えました。中国版TikTok「抖音」や小紅書(レッド)では、旅行者のトラブル体験や不満がリアルタイムで拡散し、タイ観光のイメージ悪化を加速させました。筆者がタイ市場を担当していた際も、SNS上の口コミが予約件数を左右するほどの影響力を持つことを実感しています。現代の観光では「実際に行った人の声=信頼」です。いくら政府がキャンペーンを打っても、旅行者の共感や安心感が得られなければリピートは生まれません。タイの事例は、インバウンド戦略における“ブランド信頼性”の重要性を改めて教えてくれます。
観光収入の2割を失う“依存モデル”の限界
GDPの20%が観光依存――脆弱な経済構造
日経ビジネスの記事によると観光業はタイのGDPの約20%を占め、都市によってはさらに高い割合に達しています。チェンマイでは観光関連産業への依存度が7割にのぼるという試算もあります。つまり観光客数の減少は単なる観光業界の問題ではなく、地域経済全体を直撃するリスクを抱えています。観光は裾野の広い産業ですが、裏を返せば一度バランスを崩すと、地元の雇用・物流・小売まで一気に波及する脆弱な構造でもあるのです。コロナ禍の時のタイを経験していますが、あの時ほど冷え切ったバンコクの街並みはありません。中国人観光客で賑わうエラワンの祠には人っ子一人いませんでした。
外需に頼る観光立国のリスク
タイの観光戦略は長年、外国人観光客の増加を軸に成長を続けてきました。しかし、その構造は外需依存型のモデルです。国際情勢や為替変動、そしてSNSによる評判の変化など、外部要因に左右されやすいというリスクを抱えています。コロナ禍でも明らかになったように、外からの人の流れが止まれば、経済全体が機能不全に陥ります。これは日本のインバウンドにも共通する課題であり、特定国に頼る集客モデルから脱却しなければ、同じ落とし穴にはまる可能性があります。観光を「輸出」と同じ構造で考えるのではなく、国内需要と国際需要の両輪で支える仕組みが今後のカギとなります。
タイの現実は「日本の未来」か
いまタイで起きている現象は数年後の日本を映す鏡かもしれません。日本もまた、中国人観光客が減るだけで地方経済が揺らぐ構造にあります。観光を「外国人頼み」にするのではなく、多国籍化とリピーター戦略でリスクを分散することが必要です。観光の多様化は、単に国籍を増やすだけではなく、体験や消費の“質”を高めることにもつながります。
タイの失速は「観光大国の終焉」ではなく、「新しい観光の形を模索する転換点」だと捉えるべきでしょう。日本も今こそ、自国のインバウンド構造を見直す好機です。
いま注目すべきは「親日国・タイ」市場
訪日タイ人のリピーター率は78.6%(JNTO調査)
観光大国タイが失速する一方で、日本にとって明るい材料となっているのが「親日国・タイ」の存在です。日本政府観光局(JNTO)のデータによると訪日タイ人のうち78.6%がリピーター。これはアジアの中でも突出した数字であり「一度訪れて終わり」ではなく「何度も日本を訪れる」市場であることを意味します。彼らは日本文化への理解度が高く、マナーや消費行動も安定しています。今後のインバウンド戦略では、この質の高いリピーター層をどう育てるかが鍵になります。
中間層の拡大で購買力が上昇中
タイ国内では経済発展と都市化が進み、バンコクを中心に中間層が急増しています。30〜50代のミドル層は、安定した収入と海外旅行への意欲を兼ね備えた層です。日経ビジネスの記事が示すように、中国人観光客が減少する中で、タイ人旅行者の購買力の伸びは日本観光にとって大きなチャンスです。彼らは「価格」よりも「体験」を重視し、地方や自然を感じられる旅を好む傾向があります。地域観光やサステナブルツーリズムと相性がよく、自治体や観光事業者が新たな層を開拓するうえで理想的なターゲットといえるでしょう。
SNS発信力の高さ(Facebook利用率90%以上)
タイ市場のもう一つの強みは、圧倒的なSNS発信力です。タイではFacebookの利用率が90%を超え、InstagramやTikTokも高い普及率を誇ります。TVでのニュースがFacebookからの投稿でもあります。
旅行先での写真・動画投稿が次の旅行者を生み出す「連鎖型の拡散力」があり、これが訪日観光の潜在的なPR資源になっています。筆者もタイ人KOLとのプロモーションを担当していた経験から、タイ人が自らの体験を発信する力は他国よりも強いと感じています。いま日本の観光事業者に求められているのは、こうしたタイ人の共感と拡散を生むストーリー設計です。タイは単なる「代替市場」ではなく、ポスト中国の中心となる戦略的パートナーとして位置づけるべき時期に来ています。
観光大国タイから学ぶ――持続可能なインバウンド戦略へ
“数”ではなく“質”を追求する時代へ
タイの観光失速は「観光客数を追うだけの時代」が終わりを迎えたことを示しています。日経ビジネスの記事でも観光立国としての脆弱性が指摘されていますが、これは裏を返せば、観光の質をどう高めるかという新たな競争の始まりです。筆者がタイで長年見てきたように、量を追い続けた国ほど環境負荷や価格競争に陥りやすく、観光体験の魅力が薄れてしまいます。日本も「どれだけ来たか」ではなく「どんな価値を感じて帰ったか」に目を向けるべき時です。体験価値を高める取り組みは、地域ブランドの確立にもつながります。
リピーター戦略と市場分散でリスクを減らす
一国依存から脱却するためには、リピーター戦略と市場分散の両輪が欠かせません。タイの教訓が示すように観光客の国籍が偏ると、地政学的リスクや為替変動で簡単に市場が揺らぎます。同じ旅行者が「2回目は地方へ」「3回目は体験重視」といった流れを作ることができれば消費単価の向上と地方への波及が見込めます。今後のインバウンド戦略では、短期的な集客よりも関係性を育てる観光へと転換することが重要です。
まとめ――「タイの失速」から日本が学ぶべきことと、これからの一手
観光大国タイの現状は、観光業が「数」から「質」へ転換すべきタイミングにあることを私たちに教えてくれます。
中国人観光客への過度な依存は、経済や地域観光を一瞬で揺るがすリスクをはらんでいます。
一方で日本には“親日国”タイという心強いパートナーがいます。リピーター率の高さ、SNSによる拡散力、そして日本文化への深い関心――これらは、タイ市場が「ポスト中国」として最も可能性を秘めている理由です。
しかし、単に「タイ人を増やしたい」と考えるだけでは成果は出ません。
文化・言語・価値観を理解したうえで、タイ人が“共感”し“自ら発信したくなる体験”を届けることが大切です。
そのためには、現地目線でSNS戦略を設計し、KOLとの連携を含めた包括的なマーケティング支援が欠かせません。
WITHTHAIでは、タイ語でのSNS運用・インフルエンサー(KOL)施策・訪日観光プロモーションまで、現地経験をもとに一貫支援しています。
自治体や企業がタイ人観光客を呼び込みたいと考えているなら、まずは現地感覚に根ざした戦略づくりから始めましょう。
▶ タイ人観光客向け訪日SNSマーケティングのご相談はこちら


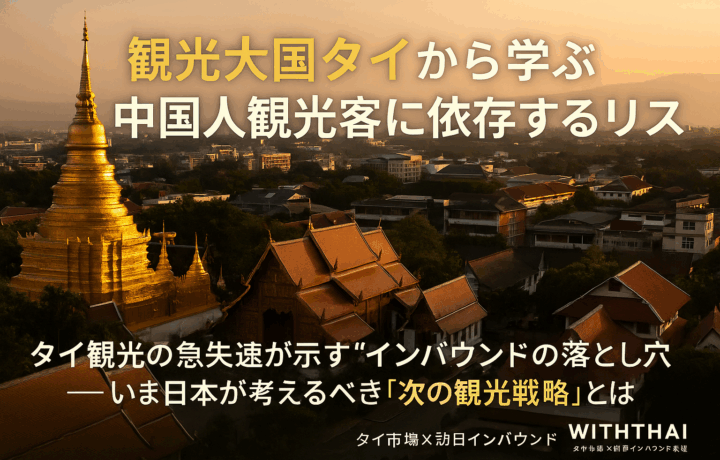


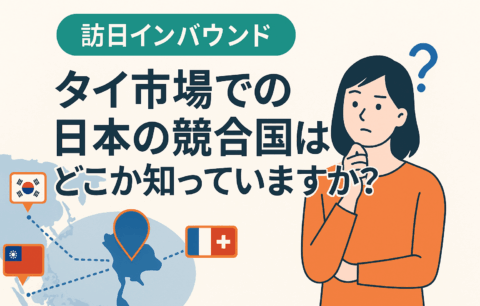

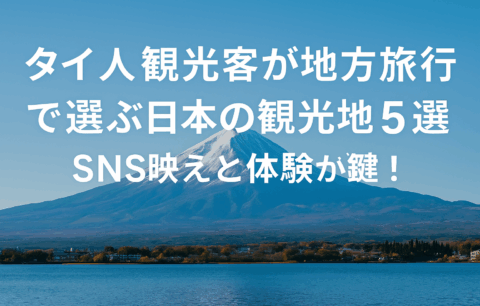






コメント