タイ向けにShopeeへ出店したものの「販売後に関税を請求されて赤字になった」という相談が急増しています。ShopeeやLazadaの越境ECは、販売者が関税とVATを負担する“DDP構造”で運用されており、購入者に税金が請求されることはありません。そのため、関税分を価格に上乗せできなければ利益がほとんど残らず、競合との価格差で苦戦するケースが多いのです。本記事ではShopeeで儲からない根本的な仕組みとタイ市場における越境ECの現実、そして日本企業が取るべき次の戦略を解説します。
ShopeeとLazadaは「販売者が関税を払う」仕組み
DDP(Delivered Duty Paid)=販売者負担の構造
DDPとは「関税支払渡し条件」を意味し、輸入国で発生する税金や通関手数料をすべて販売者が負担する契約形態です。ShopeeやLazadaの越境販売はこの条件で運営されており、購入者は支払い金額だけで商品を受け取ることができます。日本の販売者にとっては「購入者が負担するのが当然」という感覚のままでは採算が合わない点が大きな落とし穴です。
Shopeeの物流ネットワーク(Shopee Xpressなど)は、通関時に発生した関税を自動で計算し、立替払い後に販売者に請求します。販売者のアカウントから販売利益分が差し引かれるため「後から引かれていた」「理由が分からないままマイナスになった」と感じるケースも多いのです。
購入者に関税請求がいかない理由
ShopeeやLazadaがこの方式を採用しているのは、ユーザー体験を守るためです。購入者が受け取り時に追加請求を受けるとトラブルや返品が増えるため、プラットフォーム側は「購入金額=最終支払額」に統一しています。そのため、販売者がDDP方式で全額を負担することが前提となり、購入者への請求は一切行われません。販売者側が実質的に輸入者(Importer of Record)として扱われるのです。
この仕組みを理解していないと想定外のコスト負担が発生し、売上に対して利益がほとんど残らない状態になります。小規模な出店者は1件あたりの関税コストが積み上がることで資金繰りが悪化しやすく、Shopee出店の継続を断念する例も見られます。
なぜ価格を上げられないのか
ShopeeやLazadaで販売する日本企業が直面する最大の課題は「価格を上げられない」という問題です。関税やVAT(付加価値税)を販売者が負担する“DDP構造”では、本来価格に上乗せすべき税金分を反映するとタイ現地の競合商品よりも高額になってしまいます。結果として関税を吸収して販売するしかなく、薄利多売どころか赤字に陥るケースも少なくありません。
ここでは、なぜ価格を上げにくいのか、その背景を詳しく見ていきましょう。
タイ市場は極端な価格競争社会
タイのEC市場では、ShopeeとLazadaが圧倒的なシェアを占めています。どちらのプラットフォームも「セール文化」が根付いており、毎月のように“ダブルデー(11.11、12.12など)”と呼ばれる大規模キャンペーンが開催されます。その結果、ユーザーは常に値引き前提で価格を比較し、少しでも安い店舗から購入する傾向があります。
Shopee内では検索結果の並び順も「価格の安い順」で表示されることが多く、価格を下げないと露出すら減ってしまう仕組みになっています。販売者が関税や手数料を上乗せすると、検索順位が落ち、結果的に“見てもらえない商品”となってしまうのです。
個人転売・ฝากหิ้ว(ファークヒウ)文化の存在
タイでは個人による買い付け・転売文化(ฝากหิ้ว=ファークヒウ)が一般的に定着しています。これは、日本や韓国など海外で商品を購入し、タイに持ち帰ってSNS上で販売するスタイルです。個人レベルで輸入するため関税がほとんどかからず、Shopeeの正規販売者よりも2〜3割安い価格で販売できるのが特徴です。私もタイ人によく頼まれました。
日本に一時帰国するとわかると、色々頼まれ、タダでもらおうとする人もいるので一時帰国するときは黙ってました笑
この「非公式ルート」の存在が、正規販売者にとって大きな脅威となっています。日本の化粧品やお菓子などはファークヒウ販売者がスーツケースで大量に持ち帰り、InstagramやFacebookで販売するケースが多く見られます。関税も物流費もほぼゼロに近いため、ShopeeやLazadaで真面目に出店している企業は価格競争で太刀打ちできない構造に置かれているのです。
公式なのに売れないんです。
こうした非公式販売者はブランド認知度の向上に貢献する一方で、正規価格の維持を難しくしています。消費者側も「SNSで買うのが当たり前」という認識を持っているため、Shopeeの“正規販売”にこだわる理由が薄くなっているのが現状です。
正規ルート販売者が不利になる構造
結果的にShopeeやLazadaで正規に販売する企業ほど、不利な立場に立たされます。販売者は関税・VAT・手数料を負担しなければならず、価格を上げれば購入されず、下げれば赤字。非公式販売者は関税を支払わずに同一商品を安く売るため、真面目にやるほど損をする構造が生まれています。
この不均衡は越境EC特有の課題です。DDP方式では「輸入者=販売者」とみなされるため、正しい手続きを踏んだ企業だけが税金を支払い、ファークヒウ販売者のような“グレーゾーン”が価格で優位に立ってしまうのです。
ShopeeやLazadaが推奨する「購入者負担ゼロ」という方針は、消費者にとって魅力的ですが、販売者にとっては負担の大きい制度です。中小企業がこの環境で利益を確保するのは極めて難しく単に「出店=利益」にはならない現実を理解しておく必要があります。
そのため、ShopeeやLazadaを本格的な販売チャネルとして使うよりも、「どの価格帯・商品が反応を得るのか」を探るテストマーケティングの場として捉えることが現実的です。タイ市場で長期的に利益を上げるには、現地法人設立やパートナー販売など、関税負担を抑えられる構造づくりが欠かせません。
Shopeeより“現地販売体制”を整えるべき理由
ShopeeやLazadaで越境販売を行うことは、確かに手軽で始めやすい手段です。しかし、実際には関税・VAT・手数料の負担が重く、価格競争でも不利になりやすい構造です。そのため、長期的に安定した利益を確保するには、越境ECに依存せず「現地販売体制」を構築することが重要です。ここでいう現地販売体制とは、タイ国内にパートナーや代理店を持ち、現地法人や正規流通ルートを通して商品を展開する仕組みのことを指します。
Shopeeを通じた販売は“市場を知るための第一歩”としては有効ですが、実際にビジネスとして拡大するには、現地販売を軸にした体制づくりが欠かせません。以下では、その理由とメリットを3つの観点から解説します。
現地販売なら関税リスクを回避できる
越境ECでは、販売者が関税とVATを負担するDDP(Delivered Duty Paid)方式が採用されているため、販売するたびに関税が発生します。一方、現地販売体制を整えれば、輸入者(Importer of Record)を現地法人や代理店に切り替えることで、関税をまとめて管理できます。これにより取引ごとに課税される手間やコストを削減でき、安定した価格設定が可能になります。
また、現地法人を通じて輸入を行えば、税務上の控除や仕入れVATの還付が受けられるケースもあります。タイでは法人登録された企業が仕入れを行うことで支払ったVATを控除できる制度があるため、実質的な税負担を減らせます。こうした仕組みを活用することで、Shopeeで1件ずつ関税を支払うよりも効率的で、価格競争にも耐えられるコスト構造を作ることができます。
ローカルSNS(LINE・Facebook)での販売が主流
タイの消費者はShopeeやLazadaなどのECサイトだけでなく、LINE公式アカウントやFacebookページを通じた購入を好む傾向があります。LINEは月間利用者数が5,000万人を超えており、商品の問い合わせや注文、決済までを一貫して行える重要な販売チャネルです。
現地販売体制を持てば、これらのSNSを活用した「ローカルマーケティング」が可能になります。LINEでクーポン配信や限定プロモーションを実施したり、FacebookでKOL(インフルエンサー)を起用して認知を広げたりといった戦略が取れます。ShopeeやLazadaと異なり、自社ブランドの世界観や価格設定を自由にコントロールできるのが大きなメリットです。
SNS販売はリピーター獲得にも強く、ユーザーとの直接的な関係を築けます。Shopeeのように手数料がかからないため、利益率も高く維持できます。
越境ECより「現地法人+代理店販売」の方が利益率が高い
Shopeeでの越境販売よりも「現地法人や代理店を通じた販売」の方が利益率は高くなります。理由はシンプルで、関税・物流費・手数料といった中間コストが大幅に削減できるためです。Shopeeでの販売では関税やVATで売上の30〜40%が失われることもありますが、現地代理店経由なら輸入時にまとめて清算できるため、単価ごとのコストが軽くなります。
代理店販売では現地流通網を活用できるため、Shopeeのようなオンライン限定販売に比べて販路が広がります。タイではデパートやセレクトショップ、観光地の店舗などオフラインの販売力も依然として強く、「オンライン×オフライン」のハイブリッド戦略が有効です。
現地販売体制を整えることは、単に税金を減らすだけでなく「ブランドの信頼性」「継続的な収益」「現地消費者との接点」を確立することにもつながります。Shopeeを足がかりに市場を学び、最終的には現地販売へ移行する――これが、タイ市場で成功している日本企業が共通して取っているステップです。
まとめ|Shopeeは“売る場所”ではなく“テストする場所”
ShopeeやLazadaで販売する場合、販売者が関税やVATを負担する“DDP構造”である以上、価格競争の中で利益を残すのは容易ではありません。これを知らずに出店すると売上は伸びても手元に残るのはわずかという状況に陥りがちです。関税請求が販売後に発生するため、想定外のコストが後から差し引かれ、赤字になるケースが後を絶ちません。
Shopeeは越境販売の入り口として優れていますが、利益を追求する場所ではなく、市場を理解するための“テストの場”として捉えるのが現実的です。実際にどんな商品がタイ市場で注目されるのか、どの価格帯に需要があるのかを把握することで、次の戦略が見えてきます。関税構造や価格設定の仕組みを理解した上で運用すれば、Shopeeは「売る場所」ではなく、「学ぶ場所」として価値あるツールになります。
Shopeeで得た販売データやレビューは、現地での販路開拓にも役立ちます。反応がよかった商品を軸にローカルSNSや現地バイヤー営業へ展開することで、より収益性の高い販売モデルを構築できます。重要なのは、Shopeeを最終目的にしないことです。越境ECはスタート地点であり、ゴールは現地で“売れる仕組み”をつくること。この意識を持つだけで、同じShopee出店でも戦略の方向性がまったく変わります。
Shopeeは“学ぶ場所”、本命は“現地販路開拓”
Shopeeは現地市場の反応を知るためのテストマーケティングとして活用すべきです。タイの消費者がどのようなデザイン・価格・パッケージを好むのか、Shopeeで得られるレビューや販売データから多くのヒントが得られます。その情報を基に現地パートナーやバイヤーと交渉すれば、現地販売に移行するための戦略的な判断材料になります。Shopeeは目的ではなく手段。Shopeeはあくまで「入口」であり、ゴールは“タイで継続的に売れる仕組み”を築くこと。短期的な利益にとらわれず、データと現場の両面からタイ市場を育てていく姿勢が、中小企業にとって最も重要な戦略です。
タイ市場での販売を目指す日本企業の多くが、ShopeeやLazadaの関税問題でつまずいています。越境販売の採算を見直し、無理のない運用設計を行うことで、赤字リスクを最小限に抑えることが可能です。
Withthai Internationalは、ShopeeやLazadaにとどまらず、現地で実際に売れるための仕組みづくりを支援します。現地バイヤーとの商談設定、ローカルSNSマーケティング、販促翻訳、通訳手配など、販売戦略のすべてを一括でサポート。タイ語・日本語・英語の三言語対応で、現場のリアルな課題を解決します。
Shopeeでの販売を通じて市場を理解し、その次の段階で現地販路を築く。この“越境から現地へ”の流れを伴走支援するのが、Withthaiの強みです。タイ市場進出を検討している企業は、ぜひ一度ご相談ください。


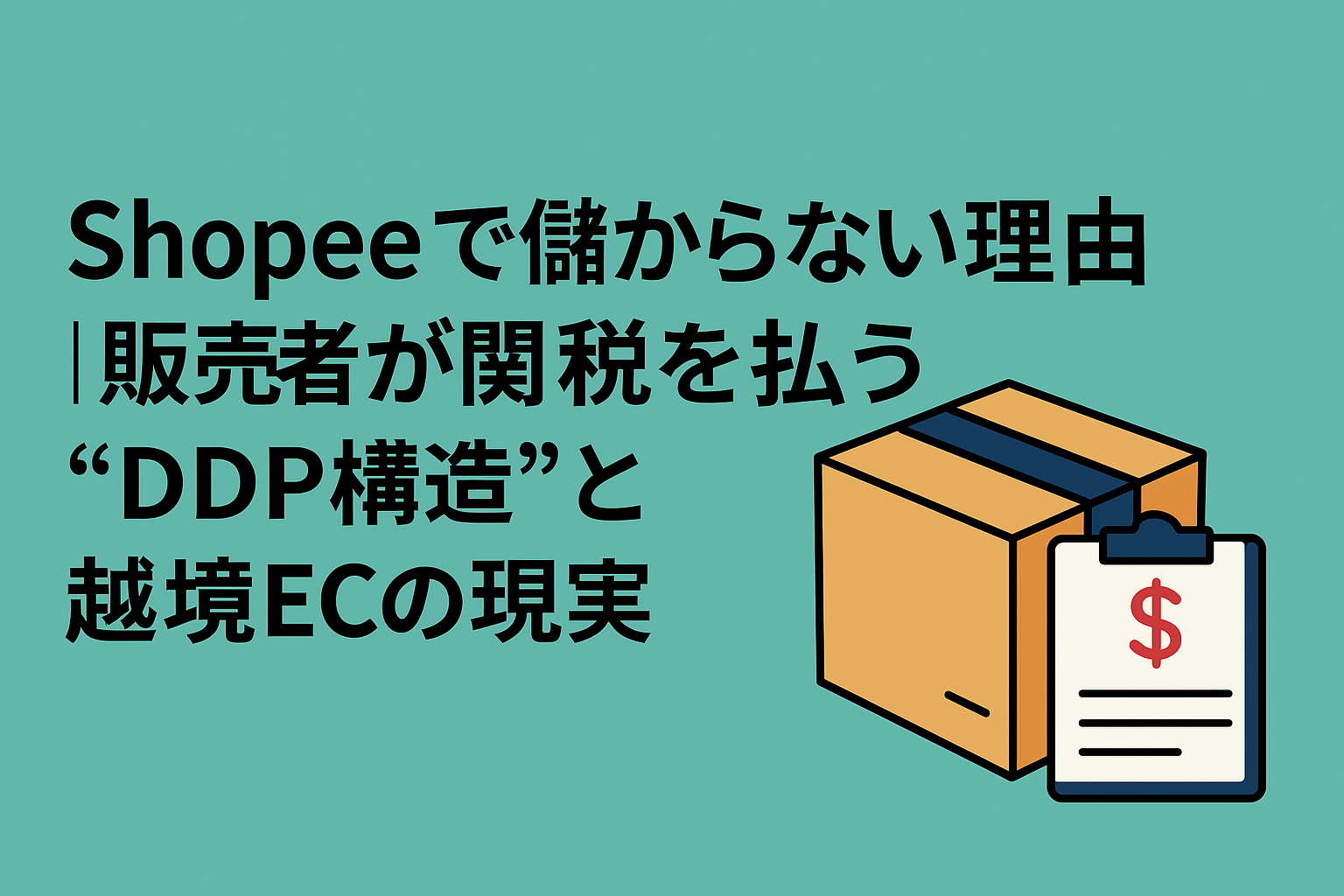
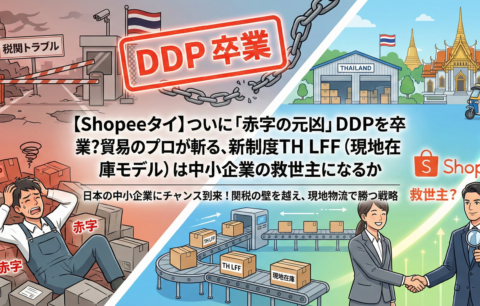

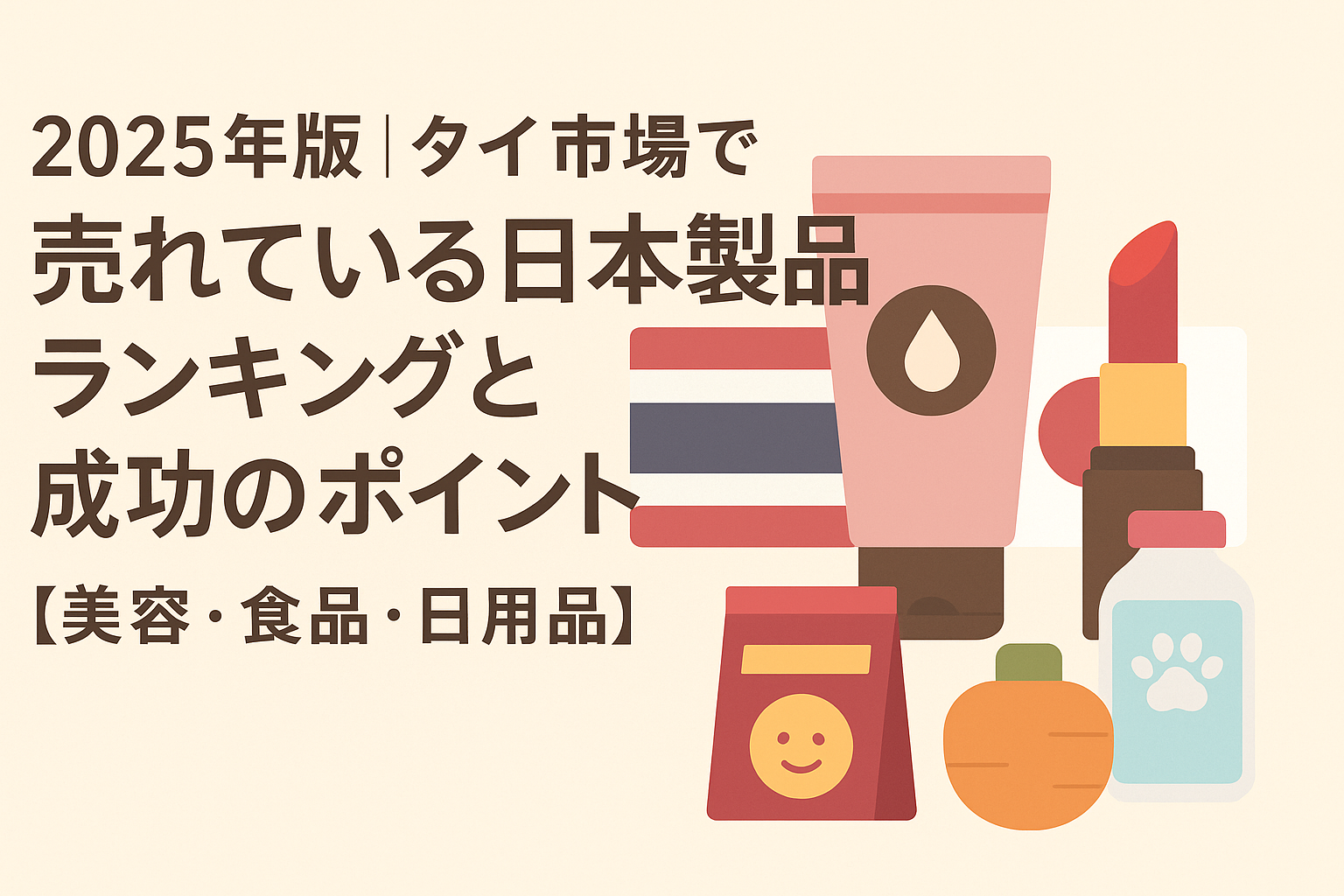
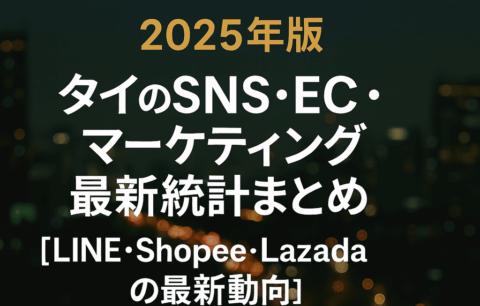
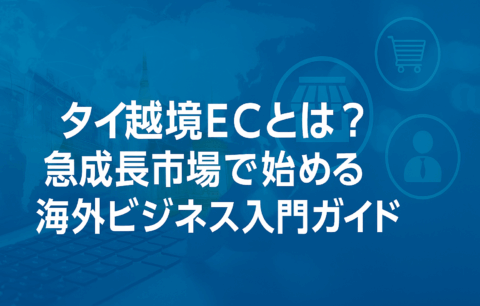

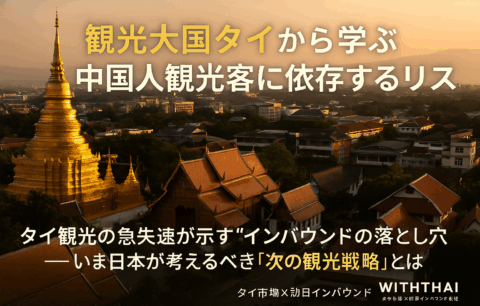




コメント