東南アジアの中心国であるタイでは、教育分野のデジタル化が急速に進み、EdTech市場はすでに約70億バーツ規模に成長しています。政府による教育DX政策やタブレット配布、ICT教育の推進が追い風となり、国内外の企業が次々と参入しています。実際、語学学校と金融大手の提携や韓国スタートアップの進出など事例は増加中です。この記事ではタイの現地メディア記事を参考に【タイ EdTech 市場】の最新動向と成長率、投資状況を整理し、日本企業にとっての参入チャンスを具体的に解説します。
【出典】
- Nation Thailand: “EdTech market in Thailand reaches 7 billion baht”
- Thairath: 「教育省がタブレット配布を推進」
- Thailand Business News: 「韓国のZep Quiz、タイ市場に正式参入」
タイEdTech市場の全体像
世界的なEdTech成長トレンド
近年、教育分野におけるデジタル化は世界的に急速な拡大を見せています。市場調査によると2020年のEdTechへの投資額は161億ドルに達し、前年から約1.3倍の成長を遂げました。中国やインドではEdTechスタートアップが次々とユニコーン企業に成長し、教育産業の中心的存在となりつつあります。AIやメタバース技術を取り入れた学習プラットフォームの普及は、従来の教室中心の教育スタイルを大きく変えています。
この動きは東南アジアにも波及しており、ASEAN諸国では教育格差の解消やデジタル人材の育成を目的にEdTech導入が加速しています。ベトナムやインドネシアではオンライン教育サービスが爆発的に利用され、政府や民間企業の投資も拡大中です。タイもまたこの世界的潮流に乗り、教育デジタル化の推進を国家戦略として位置づけています。
タイ市場規模 ― 約70億バーツに拡大
Nation Thailandの報道によると、タイのEdTech市場規模は2025年時点で約70億バーツ(約290億円)に達すると予測されています。これはコロナ禍をきっかけに学習のオンライン化が一気に進んだことが大きな要因です。さらに、タイの中間層拡大により教育への投資意欲が高まり、語学教育やスキルアップを目的としたEdTechサービスの利用が急増しています。
実務の視点で見ると、この市場規模はまだ拡大余地が大きいと考えられます。タイの教育現場ではICT導入が進みつつも、地方部では十分に普及していないため、今後の成長ポテンシャルは高いのです。また、金融や通信など異業種との連携により、教育関連サービスの利用機会が広がることも予測されます。日本企業にとっては、単に教育コンテンツを提供するだけでなく、現地企業との協業や新しいビジネスモデルを構築することが求められるでしょう。
ThaiMOOC利用者の急増と学習意欲
タイにおけるEdTech成長を象徴する事例の一つが、ThaiMOOC(Massive Open Online Course)の利用拡大です。Marketeer Onlineの調査によれば、コロナ禍前の利用者数が約26万人であったのに対し、現在では80万人以上に増加しています。この数字は、タイ人の学習意欲がオンラインを通じて大きく高まっていることを示しています。人気の分野は「IT」「ビジネス」「語学」であり、個人のスキルアップやキャリア形成に直結するテーマが選ばれています。
私自身の経験からも、タイ企業の人事部や研修担当者は、従業員のリスキル・アップスキルを強く意識しています。近年では、社内教育にEdTechを導入するケースも増えており、これは日本企業が参入する上で重要なポイントとなります。従業員教育や人材育成をテーマにしたEdTechソリューションは、タイ市場において確実に需要が拡大しています。
世界的な潮流と国内の需要拡大が相まって、タイEdTech市場は成長フェーズにあります。次章では、この市場成長をさらに後押しするタイ政府の教育DX戦略について詳しく見ていきます。
政府の教育DX戦略と政策
デジタル教室・タブレット配布プロジェクト
タイ政府は教育のデジタル化を国家戦略の柱に据えており、小中学校へのタブレット配布やデジタル教室の整備を積極的に進めています。Thairathの報道によると、教育省は数十万台規模でタブレットを配布し、全国の児童に平等な学習環境を提供することを目指しています。都市部と地方の学習環境の格差を縮小し、ICTを活用した新しい教育スタイルを普及させようという狙いがあります。
実務的な視点から言えば、こうした取り組みは教材提供や教育アプリ開発企業にとって大きな商機となります。日本企業が得意とする「正確性」「信頼性」を強みにした教育アプリや学習管理システムは、タブレットと相性が良く、現地での採用可能性が高いといえるでしょう。
ICT教育と人材育成プログラム
教育のデジタル化は単にデバイスの導入に留まらず、教師や学生のICTスキル向上を伴って初めて効果を発揮します。Nation Thailandによると、タイ政府は教育DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として、教師向けにICT研修を実施し、デジタル教材の効果的な活用法を広めています。さらに、AIやデータ分析を取り入れた人材育成プログラムも推進されており、次世代の産業に対応できる「デジタル人材」の育成が急務となっています。
教育格差の解消に向けた取り組み
タイでは都市部と地方で教育環境に大きな差が存在しています。インターネット環境や教育資源が不足する農村地域では、学習機会が十分に確保できないケースもあります。こうした課題に対し、政府はオンライン学習プラットフォームの導入や、遠隔教育システムの整備を通じて格差解消を進めています。遠隔地の学生でも均等に教育を受けられる仕組みは、教育ICTの大きな利点です。
過去に私が現地企業と協業した輸出入支援の現場でも感じたことですが、「地方部のアクセス改善」はタイの社会課題そのものでもあります。教育分野でも同様に、インフラの制約を乗り越えるサービスや、軽量で使いやすいデジタル教材には大きなニーズがあります。日本企業が現地で成功するためには、この「格差解消」という社会的テーマに沿った提案を行うことが重要です。
政府の教育DX戦略は、ハード面(デバイス・インフラ整備)とソフト面(教師研修・人材育成)の両輪で進められています。EdTech関連企業にとっては、政策と歩調を合わせることで新たな参入機会を掴むことができるでしょう。
海外企業の参入事例と成功ポイント
Wall Street English × KTC ― 教育×金融の異業種連携
タイEdTech市場における注目事例の一つが、語学学校のWall Street Englishとクレジットカード大手KTCの提携です。Nation Thailandによると、この提携によりKTCの350万口座の顧客に英語学習特典を提供し、語学教育をライフスタイルに組み込む戦略が打ち出されました。教育サービスと金融サービスが連携することで学習機会の拡大だけでなく、消費者の利便性向上や顧客囲い込みにもつながっています。
タイでは「教育は投資」という考え方が根強く、金融と教育を組み合わせたモデルは現地消費者に強く響きます。日本企業が進出する際には、このような異業種連携の発想を取り入れることで、単なる教育サービス提供に留まらず、利用者の生活に密着したEdTechモデルを構築できるでしょう。
韓国 Zep Quiz ― メタバース型EdTechの挑戦
次に注目されるのが、韓国発のEdTechプラットフォーム「Zep Quiz」のタイ市場参入です。Thailand Business Newsによると、Zep Quizはクイズ形式とメタバースを組み合わせた学習体験を提供し、インドネシアでのテスト運用では1か月で100万プレイを突破しました。すでに1,200万人以上の利用者を抱えており、同時接続5万人を可能にする技術力は大きな強みです。
タイ市場への参入にあたり、同社はタイ語対応や現地文化に合わせたコンテンツを用意し、教育を「体験型エンターテインメント」として普及させる戦略を描いています。タイの若年層がSNSやオンラインゲームに慣れ親しんでいる現状と相性が良く、教育の枠を超えた新しいEdTechの在り方を示しています。日本企業にとっても、こうした体験型・参加型の要素を取り入れることが競合との差別化につながるでしょう。
ASEAN諸国との比較(インドネシア・ベトナム)
タイEdTech市場の特徴を理解するには、ASEAN諸国との比較も欠かせません。インドネシアでは人口規模の大きさを背景に、教育アプリやオンライン学習サービスの利用が急速に拡大しています。語学教育やK12教育(義務教育段階)分野でのスタートアップの成長は著しく、多額の投資が集まっています。一方、ベトナムでは政府がICT教育を強力に推進し、国際大学との提携や職業教育分野のEdTechが注目を集めています。
これらの国々と比較すると、タイは一人当たりGDPが高く、中間層による教育投資が活発である点が強みです。そのため、プレミアムな教育コンテンツや質の高い学習サービスが受け入れられやすい市場といえます。ただし、地方との教育格差やインフラ面の課題は依然として存在するため、参入企業は現地適応力を持ったサービス提供が求められます。
海外企業の参入事例はタイEdTech市場の成長性を示すものであり、日本企業にとっても参入戦略を考える上で参考になるポイントが多くあります。「異業種連携」「体験型EdTech」「現地適応」は、今後の成功に不可欠な要素になるでしょう。
タイEdTech市場の特徴と課題
中間層の拡大と教育投資の増加
タイEdTech市場の成長を支えているのは、中間層の拡大と教育に対する投資意欲の高まりです。タイは一人当たりGDPが7,000ドルを超え、東南アジアの中でも比較的購買力の高い市場に位置づけられています。都市部の家庭では「教育は最大の投資」という考え方が根強く、子どもへの英語教育やデジタルスキル習得のために積極的にお金をかける傾向が見られます。
この需要はEdTechサービスの拡大に直結しており、オンライン英語学習、STEM教育、AIを活用したパーソナライズ学習など、多様な分野のサービスが市場に参入しています。タイの消費者は「実績や信頼性」を重視する一方で、「楽しさ」「学びやすさ」も購買判断の大きな要素になります。したがって、日本企業が参入する際には、品質の高さと同時にユーザー体験を工夫することが重要になります。
都市と地方の教育格差
一方で、タイのEdTech市場には都市と地方の教育格差という課題が残されています。バンコクやチェンマイ、プーケットといった都市部では高速インターネットやデジタルデバイスが普及している一方、地方の農村地域では接続環境が整っていない学校も少なくありません。Thairathの記事によると、政府はタブレット配布やデジタル教室の設置を進めていますが、インフラ不足による利用制約は依然として大きな障害となっています。
現場の声としても、地方の学校では「デバイスはあるが教師が使いこなせない」「通信環境が不安定でオンライン授業が中断される」といった問題が頻繁に聞かれます。日本企業が現地で展開する場合には、こうした教育格差を埋めるための支援策、オフライン利用可能な教材や軽量なアプリ開発などが競争優位性を発揮するポイントになるでしょう。
インフラ・決済環境の制約
インフラと決済環境の制約もタイEdTech市場の課題です。インターネットの普及率は高まっているものの、依然として地域差が大きく、教育ICTの活用を阻む要因となっています。さらに、学習アプリやオンライン講座の支払いに関しても、クレジットカードを持たない層が一定数存在し、月額課金モデルの導入に壁があるのが実情です。
近年ではモバイル決済やQRコード決済が急速に普及していますが、教育分野での対応はまだ発展途上にあります。この点については、日本企業がタイ市場に進出する際の大きな検討ポイントになるでしょう。現地の決済習慣に対応した柔軟な価格モデルやプリペイド方式を導入すれば、利用者層を大きく拡大できる可能性があります。
日本企業にとっての参入チャンス
日本EdTechの強み(品質・信頼性)
タイEdTech市場において、日本企業の大きな強みは「品質」と「信頼性」です。日本の教育サービスや教材は、正確さや継続性において高い評価を得ています。Nation Thailandなどの現地メディアも指摘するように、タイでは教育は「将来への投資」と捉えられており、保護者や学生は価格よりも学習効果や信頼性を重視する傾向があります。そのため、教育コンテンツや学習管理システムにおいて高品質を維持できる日本企業は、現地市場で強い競争力を発揮できるでしょう。
教育分野で日本企業が参入する際にも、単にサービスを提供するだけでなく、品質保証やサポート体制を明確に示すことで、現地教育機関や保護者からの信頼を獲得しやすくなります。
現地化の重要性(タイ語対応・カリキュラム適応)
一方で、日本企業が成功するためには「現地化」が不可欠です。タイの教育現場では、タイ語による教材や指導が必須であり、グローバルで通用するサービスであっても、タイ語対応が十分でなければ利用者の拡大は難しいでしょう。また、タイの教育カリキュラムや評価方法に沿ったサービス設計が求められます。
Thairathの記事によると、政府は教育DXを推進する中で「ICT教育をカリキュラムに統合」する動きを強めています。この点に対応できる企業は、政府や学校との連携を進めやすくなります。日本のEdTech企業が提供する教材を「タイの学習指導要領」に合わせて調整すれば、現地での受け入れは格段に高まります。私がこれまで現地で見てきた輸出入ビジネスと同じように、サービスの「ローカライズ」が成功のカギです。
B2B/B2G連携による展開可能性
さらに注目すべきは、B2CだけでなくB2BやB2Gの展開可能性です。タイのEdTech市場は個人利用が増加している一方で、学校や企業研修、さらには政府プロジェクトを通じた導入が拡大しています。Thailand Business Newsによると、韓国のZep Quizはタイ語対応を進めつつ、教育省や学校と連携する戦略を描いており、これは日本企業にも参考になります。
日本企業が進出する際も、教育省や地方自治体といった公的機関との連携を図ることで、大規模な市場を開拓することができます。教育格差の是正や人材育成といったテーマは政府の重点政策であり、この分野に合致するサービスは採択されやすいと考えられます。また、民間企業の人材育成ニーズも高まっているため、B2Bでの企業研修向けソリューションを提供するのも有効です。
まとめ
タイEdTech市場は、政府の教育DX政策やタブレット配布プロジェクトを追い風に急成長を遂げています。Nation Thailandによると、市場規模はすでに約70億バーツに拡大しており、今後も利用者や投資が増加すると予測されています。Wall Street English × KTCの提携や韓国Zep Quizの進出など、海外企業の参入事例が増えていることも、この市場が国際的に注目されている証拠です。まさに「成長フェーズ」の真っただ中にあると言えるでしょう。
日本企業が今動くべき理由
こうした動きの中で日本企業にとっては「今」が参入の好機です。高品質で信頼性の高い日本のEdTechはタイ市場との親和性が高く、現地化やB2B/B2G連携を進めれば十分に勝機があります。ただし、言語対応や商習慣の違いなど参入にはハードルも存在します。
私は18年間タイに在住し、13年間にわたりタイ支店で海外営業を担当してきました。現在は中小企業のタイ進出や販路開拓、輸出入の実務支援を行っています。タイEdTech市場への進出を検討されている企業の方には、市場調査から現地企業との交渉、実務サポートまで一貫してお手伝いが可能です。
タイEdTech市場に挑戦したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の強みを最大限に生かした形で、タイでのビジネス展開をサポートいたします。


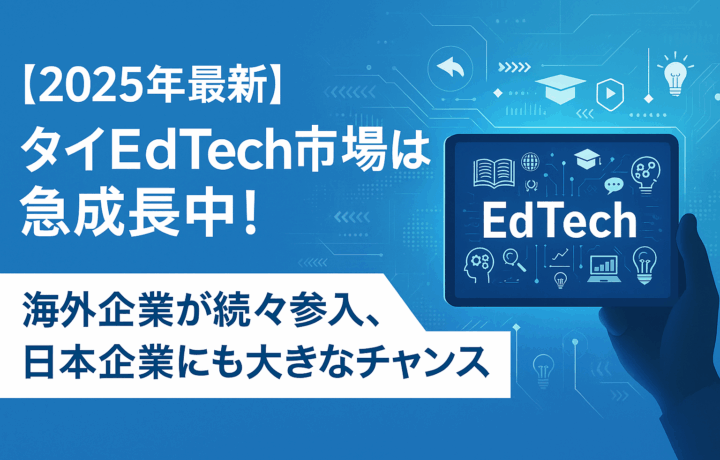


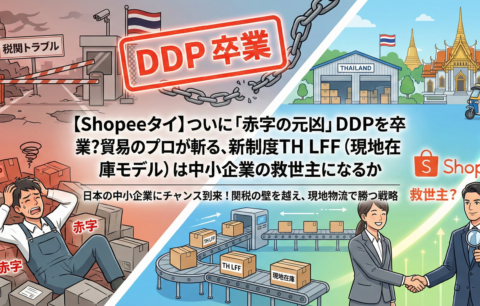
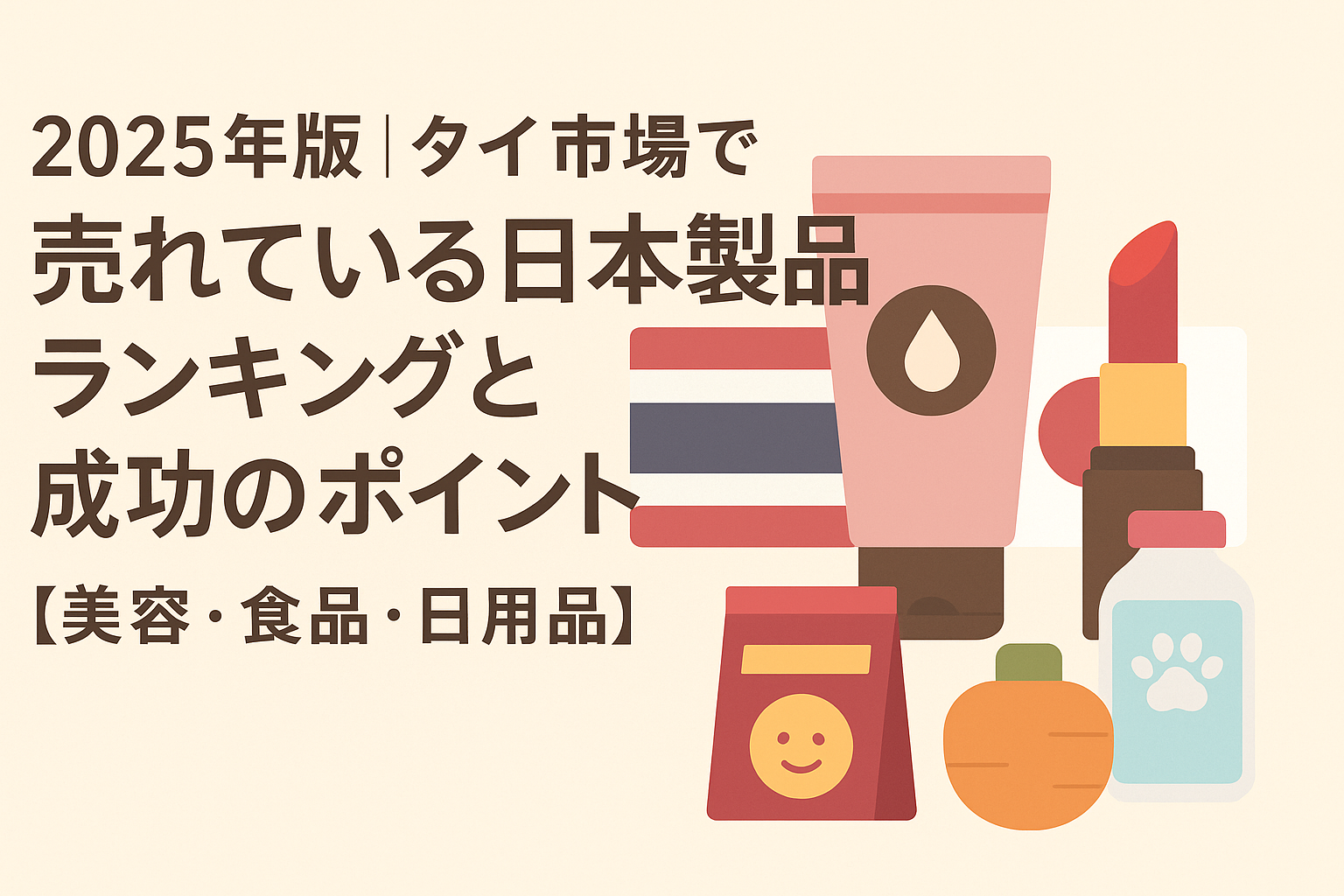





コメント