東南アジアの成長市場として注目を集めるタイにおいて、日本企業の投資が再び加速しています。タイ現地メディアの報道(LINE TODAY, 2025年7月)によれば、BOI(タイ投資委員会)とJETROが会合を開き、自動車、エレクトロニクス、食品など5大分野で日系企業の投資が拡大していることを強調しました。ASEAN市場のハブとしての地理的優位に加え、タイ国内の消費力向上も追い風となり、中小企業にとっても新たなビジネスチャンスが広がっています。本記事では、この現地報道をもとに、日本企業の投資動向と注目分野、そして中小企業が成功するためのポイントを解説します。
なぜ今、日本企業はタイ市場に注目しているのか
ASEAN市場のハブとしての地理的優位
タイは東南アジアの中心に位置し、陸路・空路・海路のアクセスに優れています。LINE TODAYの記事によると、BOI(タイ投資委員会)は日本企業に対し「ASEAN全域へのゲートウェイとしての役割」を強調しています。実際、タイに拠点を構えることでベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーといった周辺国への展開が容易になり、ASEAN市場全体を見据えたサプライチェーンの構築が可能です。私自身も過去にタイからラオスやミャンマーへ商品を輸出する業務を担当しており、その利便性を実感してきました。中小企業にとっても、この「拠点を置けば周辺国へ広がる」という地理的強みは大きな魅力といえます。
サプライチェーン再編での重要性
世界的にサプライチェーンの再編が進む中、タイは「生産拠点」として再び脚光を浴びています。自動車産業では、EVやハイブリッド関連の新規投資が増加しており、日本企業がその中核を担っています。記事でもBOIが強調するように、日本は過去10年間でタイ最大の投資国であり、その累計投資額は7兆バーツを超えています。私の経験上、タイは部品調達や人材確保に強みを持ち、日本と比較して人件費が抑えられる点も中小企業にとって大きなメリットです。ASEAN域内での自由貿易協定により関税面で優遇を受けられるため、製造から輸出までの流れを効率化できるのです。
タイ国内消費市場の成長ポテンシャル
もう一つ見逃せないのが、タイ国内市場そのものの成長です。人口約7,000万人の消費市場は近年、所得水準の向上により購買力が拡大しています。健康志向食品や日本食、医療関連サービスは高い需要が見込まれます。LINE TODAYの記事でも、食品や医療分野が今後の注目分野として挙げられていました。タイ人消費者は「高品質で安心できる日本製品」に対する信頼が強く、中小企業にとっては差別化しやすい市場です。消費者ニーズを正しく理解し、現地のパートナーを通じて販路を築くことで、安定した売上を見込むことができます。
こうした要素から日本企業がタイ市場に注目する理由は明らかです。ASEANのハブ、サプライチェーンの拠点、そして拡大する消費市場。この三つの要素が揃っているからこそ、中小企業にとっても大きなチャンスが存在します。
BOIが示す5大投資分野とビジネスチャンス
自動車産業(EV・ハイブリッド車への注力)
LINE TODAYの記事によると、BOI(タイ投資委員会)は自動車産業を引き続き重点分野と位置づけています。EV(電気自動車)やハイブリッド車への投資を強化しており、日本企業もこれに積極的に参入しています。タイ政府は2030年までに国内生産車の30%をEVにする目標を掲げており、バッテリーや充電インフラなど周辺分野にも広いビジネスチャンスがあります。私自身、現地で自動車部品メーカーと取引をしてきましたが、タイ国内のサプライチェーンは発達しており、中小企業にとっても「部品供給の一部を担う」「メンテナンス関連事業を展開する」といった入り口が現実的です。
エレクトロニクスと次世代デバイス
次に注目されるのがエレクトロニクス分野です。記事によれば、タイは半導体や電子部品の製造拠点として日系企業からの投資が拡大しています。IoTや5G関連デバイスの需要はASEAN全体で急増しており、タイを生産拠点とすることで広域輸出が可能になります。タイは電子部品輸出に強いインフラと人材を持っており、日本企業が求める品質管理も比較的スムーズに導入できます。大手企業が進出する一方で、中小企業にも「特定用途向けの部品」「高付加価値の小ロット生産」といった分野で十分に勝機があるでしょう。
機械・部品産業の高度化
BOIは機械産業についても「高度化」を推進しており、自動化や精密部品の分野で投資が増えています。タイは製造業全体がGDPの約30%を占める産業国家であり、機械の需要は国内外で根強いのが特徴です。私が商社時代に担当していた輸出入でも、タイ向けに日本製機械を供給する案件は多く、現地企業からの信頼も厚い分野です。中小企業にとっては「既存機械のメンテナンス」「特殊部品の供給」といったニッチな分野で参入しやすく、現地パートナーを通じた販路開拓が有効です。
食品・加工品の輸出拡大
記事では食品分野も今後の重点領域として紹介されています。タイは農産物の生産国でありながら、日本食や高品質な加工品への需要が急拡大しています。健康志向や日本食ブームを背景に日本からの食品輸出は追い風となっています。私は過去にタイの大手スーパーとの取引を担当した経験がありますが、日本酒、調味料、スナック菓子などは現地消費者のリピーター率が高く、中小企業の商品でも十分に市場に浸透できることを実感しました。食品ビジネスはブランド力よりも「安心・安全」「ストーリー性」が重視されるため、現地での販売戦略がカギとなります。
医療・バイオ製品分野の成長
最後にBOIが注目するのが医療・バイオ産業です。記事によると、タイ政府は医療ツーリズムを国家戦略の一つとして推進しており、医薬品や医療機器、バイオ関連製品への投資が加速しています。私の見立てでは、日本企業が持つ高品質な医療機器や健康食品はタイ人消費者から強い信頼を得やすく、中小企業にとっても大きなチャンスです。また、バイオ製品分野は政府の支援も手厚く、輸出ビジネスに直結する可能性があります。今後は「日本製=安心・高品質」というイメージを活かし、医療・健康領域での販路拡大が期待されます。
これら5つの分野は、いずれも日本企業の強みと親和性が高く、中小企業にとっても市場参入のチャンスが広がっています。BOIが示す方向性を理解し、自社の強みを重ね合わせることがタイ市場での成功の第一歩になるのです。
JETRO・JCC調査から見る日本企業の投資動向
投資件数・金額から見る日本企業の存在感
LINE TODAYの記事によると、BOI(タイ投資委員会)は過去10年間(2015年~2025年6月)で、日本からの投資案件が2,620件、総額7兆バーツを超えていると発表しました。これはタイにとって日本が最大の投資国であり続けていることを示しています。私が商社時代に現地で肌で感じてきたのも、日本企業のプレゼンスの強さです。製造業からサービス業まで幅広い分野に日本企業が進出しており、現地の産業基盤を下支えしているのが実情です。数字は大企業を中心としていますが、その投資の裾野には中小企業のサプライヤーや関連ビジネスが数多く関わっており、参入余地は大きいといえます。
投資意欲を支える要因(政策・制度・市場環境)
ではなぜ日本企業はこれほどタイに投資を続けているのでしょうか。記事でも触れられているように背景にはタイ政府の投資優遇政策が存在します。BOIによる法人税免除や輸入関税の軽減、外資規制の緩和などは進出企業にとって大きなメリットです。また、ASEAN域内の自由貿易協定(AFTA)を活用することで、タイを拠点に周辺国への輸出を効率的に行える点も魅力です。インフラ整備が進む「EEC(東部経済回廊)」は次世代産業の集積地として注目され、日本企業のR&D拠点や製造拠点の誘致が加速しています。制度の恩恵を受けながら現地パートナーと連携し、税制や労務のリスクを抑えた事業展開をすることが成功のポイントでした。
中小企業に広がる参入機会
投資額の大きな話は一見「大企業だけのもの」と感じられるかもしれません。しかし実際には、大手企業の投資に伴い、中小企業にとっても参入チャンスが広がっています。自動車産業でのEVシフトは部品サプライヤーの入れ替えを促しており、日本の中小メーカーにも新しい商機があります。食品や医療分野でも、日本製品に対する「高品質・安心」の評価が強く、中小規模でも十分に勝負可能です。私が現地でサポートしてきた事例でも、現地の販売網や商習慣に合わせた戦略を取れば、中小企業でも安定的に販路を築けることを実感しています。市場参入にあたっては、制度や文化の違いを理解し、現地ネットワークをうまく活用することが欠かせません。
このようにJETROやJCCが示す調査データは「大企業の動き」だけでなく、「中小企業にも十分に開かれた機会がある」ことを示しています。タイ市場参入を検討する企業にとって、こうした最新の投資動向を踏まえた戦略設計は不可欠です。
中小企業がタイに参入する際の課題
言語・商習慣の壁と商談リスク
タイ市場参入を考える際に最初に直面するのが「言語」と「商習慣」の壁です。LINE TODAYの記事でも、日本企業が進出するうえで現地の文化理解が重要であると指摘されています。私はタイ語を駆使しながら現地企業と取引をしてきましたが、日本と同じ感覚で交渉を進めると誤解を生むケースが多くあります。合意形成に時間がかかる、取引条件に柔軟性を求められるなど、日本とは異なるビジネス慣習があります。言葉の壁があると、こうしたニュアンスを見落としやすく、商談が不利に進むリスクがあります。そのため、通訳やコーディネーターを活用しつつ、現地の文化に沿ったコミュニケーションを取ることが不可欠です。
BOI申請・税制・労務などの法規制
次に大きな課題となるのが、制度や法規制の理解と対応です。BOI(タイ投資委員会)の優遇制度を活用すれば、法人税の免除や輸入関税の軽減などメリットは大きいものの、申請には詳細な書類や現地担当官とのやり取りが必要です。記事でも「投資優遇の手続きが整備されつつある」と触れられていましたが、現実には中小企業にとって煩雑で時間のかかる作業です。また、税制や労務管理についても、日本と異なるルールが数多くあります。解雇規制が厳しい、残業代の扱いが異なるなど、知らずに進出すると後で大きなコスト増につながるケースがあります。専門家や現地の信頼できる会計・法務パートナーを選定し、事前にリスクを洗い出すことが大切です。
現地パートナー・販路開拓の難しさ
最後に、中小企業にとって最も大きな課題は「販路開拓」です。タイは市場規模が大きく、投資意欲のある日本企業も多数存在しますが、実際に販売網を築くには現地流通業者や販売パートナーとの連携が欠かせません。LINE TODAYの記事が示すように、大手企業は既に広いネットワークを確保していますが、中小企業の場合はその分不利になりやすいのです。私がこれまで支援してきた事例でも、単に商品を持ち込むだけでは販売につながらず、現地市場に合わせた価格戦略やプロモーションが必要でした。食品や消費財の場合、FDA登録や現地マーケティングを伴わなければ認知を得るのは難しいのが実情です。販路を開拓する際には、現地でのネットワーク構築や信頼関係づくりを重視することが不可欠です。
こうした課題は一見ハードルが高いように思えますが、正しい情報と現地でのサポート体制があれば乗り越えることが可能です。タイ進出を検討する中小企業は、これらのリスクを事前に把握し、戦略的に準備を進めることが成功への近道になります。
販路開拓を成功させるための3つのポイント
BOI優遇制度を活用する方法
タイにおける販路開拓で重要なカギを握るのが、BOI(タイ投資委員会)の優遇制度です。LINE TODAYの記事によると、BOIは日本企業に向けて法人税の免除や関税軽減などのインセンティブを積極的に提供しており、過去10年間で日本は最大の投資国となっています。制度を理解していない企業が進出した場合、税制面で大きな差が出ることがあります。食品や医療関連分野でBOIの承認を得ると、輸入にかかるコストが抑えられるだけでなく、労働許可証やビザの取得もスムーズになります。こうした仕組みを早期に活用することが、事業立ち上げのスピードと収益性に直結します。
現地ネットワークを使った営業アプローチ
販路開拓を進める上で避けて通れないのが「現地ネットワークの構築」です。記事でも指摘されている通り、タイ市場は大手企業が先行している分、信頼できるパートナーや販売チャネルを持つことが中小企業には不可欠です。商社時代に多くの商談を現地企業と共に進めましたが、信頼関係を築けた場合、紹介や口コミで販路が広がることも少なくありませんでした。食品や消費財は、卸業者や小売店との関係構築が大切です。単発の取引にとどまらず、展示会や業界イベントへの参加を通じて現地ネットワークを拡大することが、中小企業の市場参入を加速させる現実的な方法です。
タイ消費者ニーズを理解した商品戦略
販路を築いても現地の消費者に受け入れられなければ成功は望めません。タイの消費市場は拡大を続けており、記事でも「食品・医療・自動車」など幅広い分野が注目されていると紹介されています。現地で感じるのは、タイ人消費者は「品質・安心感」に加えて「価格バランス」と「タイ人好みのデザインや味付け」を重視する傾向があるという点です。日本食ブームで抹茶や日本酒の需要が高まっていますが、パッケージをタイ語表記にする、価格帯を中間層が手に取りやすいレベルに設定するなど、細やかな調整が成功のポイントになります。単に「日本製だから売れる」わけではなく、タイ人の生活スタイルや嗜好に寄り添った商品戦略が不可欠です。
この3つの視点を押さえることで、中小企業でもタイ市場での販路開拓を成功に導くことが可能です。「制度の活用」「ネットワーク構築」「消費者理解」の3本柱を意識することで、競争力ある市場参入が実現できます。
まとめ|今こそタイ市場に挑戦すべき理由と支援サービス
日系大手の動きに追随するメリット
LINE TODAYの記事によると、BOI(タイ投資委員会)は過去10年間で日本からの投資件数が2,600件を超え、依然として日本が最大の投資国であることを強調しています。こうした大手企業の積極的な動きは「市場が成熟しつつある証拠」であり、中小企業にとってはその後を追随することで、現地のエコシステムに参入しやすくなるメリットがあります。大企業が整備したサプライチェーンや流通網を活用できるのは、中小規模の企業にとって大きなアドバンテージです。
中小企業でも勝負できるニッチ分野
一方で、すべてを大手と同じ土俵で戦う必要はありません。タイ市場では、健康志向食品、機能性部品、デザイン性の高い消費財など、ニッチながら確実に需要がある分野が存在します。「日本製の信頼性」と「中小企業ならではの柔軟な対応力」を組み合わせることで、むしろ大手では対応しきれない隙間市場を獲得できるケースが多々あります。小規模だからこそ、現地の細かなニーズに合わせた商品開発やサービス提供が可能なのです。
【サービス紹介】現地経験18年のサポートでリスクを最小化
とはいえ、言語や商習慣、制度面の壁を一企業だけで乗り越えるのは容易ではありません。私はタイに18年在住し、商社で13年間にわたり輸出入と現地営業に携わってきました。その経験を活かし、現在は中小企業向けに「販路開拓」「BOI申請サポート」「商談アテンド」などをワンストップで提供しています。タイ市場参入において最も大切なのは「情報」と「信頼できるパートナー」です。リスクを最小化しながら効率的に販路を広げたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
👉 無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。



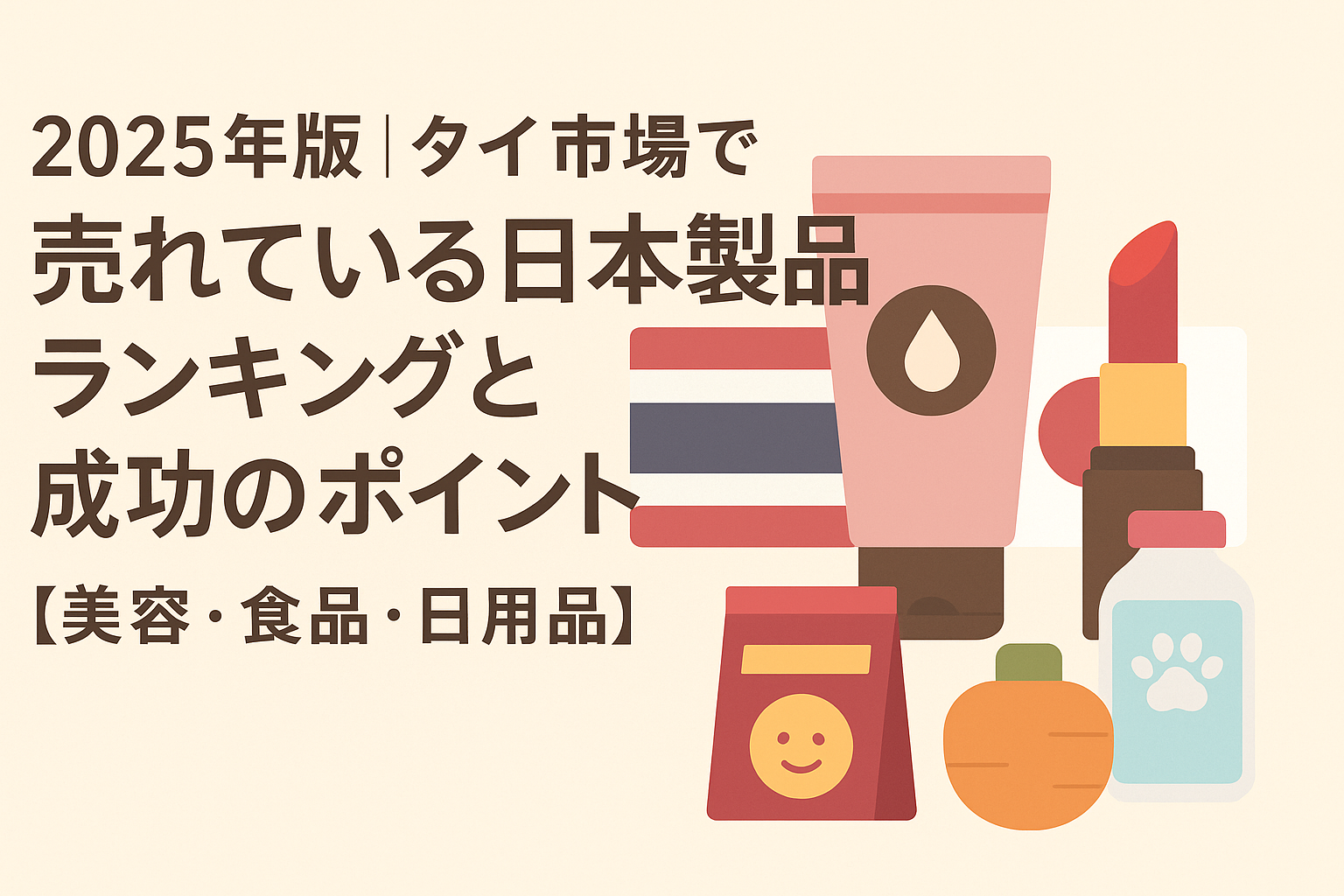
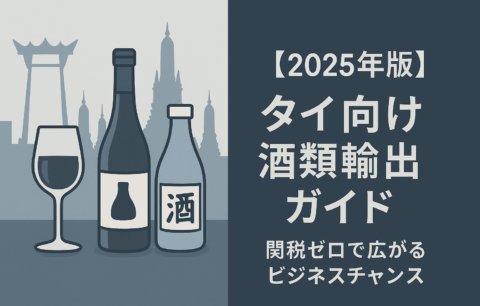





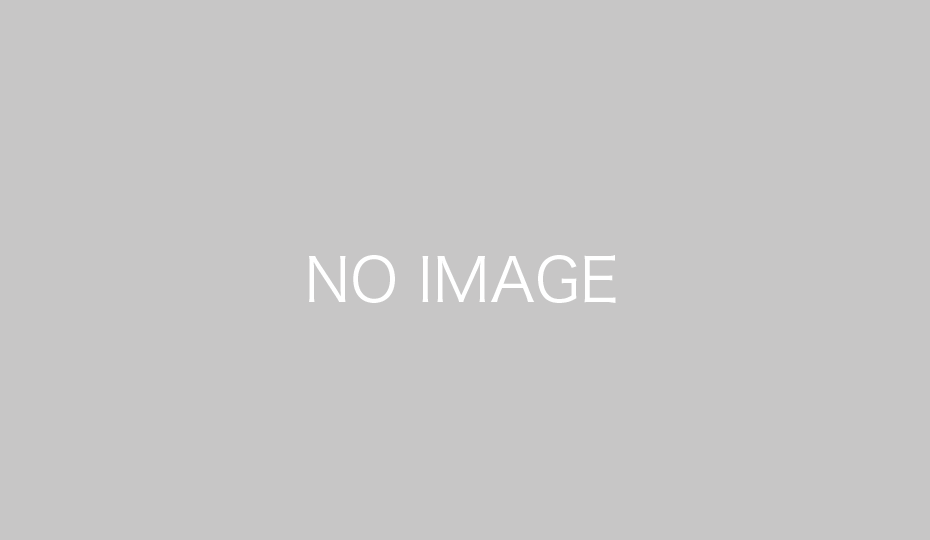



コメント