タイに自社製品を売りたいが、関税がよく分からない」「調べ方が難しい」──そう感じていませんか?タイはASEANの物流ハブとして注目されており、多くの日本企業が輸出拡大を狙っています。
しかし、関税やVAT、FTA制度の知識がないまま進出すると、コスト試算や価格設定に大きな影響が出る恐れも。
本記事では、中小企業の海外営業を支援してきた実務経験を活かし、タイ輸出に関わる関税制度、調べ方、リスク管理までを分かりやすく解説します。
タイへの輸出で知っておくべき関税の基本知識
タイへの輸出ビジネスを考える上で、避けて通れないのが「関税」です。これは、商品を他国に送り込む際に発生する費用の一つですので、きちんと理解しないといけません。タイへの輸出においてどのような税金がかかるのかを理解していきましょう。
関税とは?輸入時に課される代表的な税金
関税とは、ある国に商品を輸入する際に課される税金のことです。タイに限らず、多くの国では自国産業を保護するため、また国家財政の一部を補うために関税制度が導入されています。関税は、通常「商品の輸入価格(CIF価格)」を基準に課され、商品ごとに定められた関税率を掛けて計算されます。例えば、CIF価格が1,000ドルで関税率が10%の場合、関税は100ドルとなります。関税の適用対象や税率は、輸入品の種類や原産国、さらには協定の有無によって異なるため、タイ向け輸出を検討する際には、正確な情報の取得が重要です。
タイにおけるVAT(付加価値税)とその仕組み
タイに商品を輸出する際、関税だけでなく他の税金も発生します。代表的なのが「付加価値税(VAT)」です。VATは日本の消費税にあたるもので、タイでは現在7%が一般的です(特定の品目には免税や軽減税率が適用される場合もあります)。輸入時には、この関税とVAT、そして場合によっては物品税や特別消費税などが課せられることがあります。これらの税金が合計でいくらになるかを正確に把握することが適正な価格設定やビジネス計画を立てる上で不可欠です。
タイ関税制度の全体像と税率の計算方法
タイの関税制度は、日本とは異なる部分も多いです。ここではタイの関税制度を構成する主要な要素について詳しく見ていきましょう。
タイ関税局(Customs Department)の役割
タイにおける関税の取り扱いは、財務省の下にある「タイ関税局(Customs Department)」が所管しています。この関税局は、輸入・輸出に関わる関税の徴収や通関の監督、密輸防止、関税制度の運用全般を担っています。輸出者が輸出先での税制を正確に把握するためには、タイ関税局の公式ウェブサイトや、日本語対応が可能な専門窓口に問い合わせることが推奨されます。実際の税率情報やHSコードの分類についても、関税局が提供する最新の資料を参考にすることが重要です。
HSコードによる品目分類と注意点
タイの関税体系は、世界中で採用されている「HSコード(Harmonized System Code:国際統一商品分類システム)」に基づいています。HSコードとは、貿易されるすべての品目を共通の番号で分類するための国際的なシステムで、これにより各国間で商品の種類を正確に特定し、適切な関税率を適用することが可能になります。あなたの輸出しようとしている商品がどのHSコードに該当するかによって、適用される関税率が大きく変わるため、このコードの正確な特定が重要です。誤ったHSコードを申告すると、過徴収や追徴課税のリスクがあるため、細心の注意を払う必要があります。ただし、国によっては異なるHSコードになる場合があります。
関税の種類(従価税・従量税)と課税対象の考え方
タイで課される関税には、主に以下の2種類があります。
従価税:輸入品の価格(課税標準)に対して一定の税率をかける方式です。例えば、価格の10%が関税、といった形です。タイの関税の多くはこの従価税です。
従量税:輸入品の数量(重量、容積、個数など)に対して一定の金額をかける方式です。例えば、1kgあたり〇〇バーツ、といった形です。
特定の品目には、これらの両方が適用される複合税率や、特定の目的のために課される特定の税金(例えば、奢侈品に対する高関税など)が存在することもあります。輸出品目に応じて、どの関税がどの税率でかかるのかを事前に把握しておくことが、コスト計算の基本となります。
私が商社時代に取り扱っていた潤滑油などは、まさに従価税と従量税(物品税)がかけられてました。
関税率の調べ方とFTA/EPA活用の具体策
World TariffとRules of Origin Facilitatorの使い方
「World Tariff」は、関税率や輸入規制に関する情報を国別・品目別に検索できる国際的な有料データベースです。日本ではジェトロ(日本貿易振興機構)が法人向けに提供しており、日系企業にとって信頼性の高い情報源といえます。タイ向けの関税率を調べる場合、輸出したい商品のHSコードを入力することで、適用される関税率や付加価値税(VAT)などの詳細が一覧で確認できます。現地の関税分類に準じたデータが反映されているため、タイ税関での実務に即した情報が得られるのが特長です。
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
「Rules of Origin Facilitator」は、国際貿易センター(ITC)が提供する無料のオンラインツールで、各国の関税優遇制度や原産地規則を調べることができます。特にタイと日本間ではEPA(経済連携協定)が発効されており、原産地が日本であることを証明できれば、関税が大幅に軽減または免除されるケースもあります。本ツールでは、品目のHSコードと輸出入対象国を入力するだけで、適用される優遇制度と必要な証明書の情報が表示されるため、FTA/EPA活用を検討する企業にとって非常に有効です。
タイ税関の事前教示制度の活用方法
最も確実な方法のひとつが、タイ税関による「事前教示制度(Advance Ruling)」を活用することです。これは輸出予定の商品について、事前にタイ税関に問い合わせることで、関税分類や税率を公式に確認できる制度です。事前教示を取得しておけば、輸出時の通関でのトラブルを未然に防ぐことができ、コストや納期の見通しも立てやすくなります。書類は英語またはタイ語での提出が求められますが、現地での実務経験が豊富な専門家や通関業者に依頼することでスムーズに対応可能です。
タイの税関のサイトで調べられます。
Integrated Tariff Database.itd.customs.go.th
日本とタイの関税協定と適用条件
タイへの輸出において、関税コストを削減し、競争力を高めるためには、日本とタイが締結している各種関税協定や特別措置を理解し、活用することがが大事です。
日タイEPA(経済連携協定)通称JTEPAとは
日タイ経済連携協定(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)は、日本とタイの間で貿易や投資を促進するために締結された協定です。この協定のメリットは、特定品目において関税が撤廃または大幅に削減される点にあります。自社製品がこの協定の対象品目であり、かつ原産地規則を満たしている場合、より有利な条件でタイ市場に参入できるようになります。このEPAを活用することで、コスト競争力を高め、ビジネスチャンスを広げることができます。
RCEP(地域的包括的経済連携協定)とは
RCEPは、2022年に発効したアジア太平洋地域の包括的な自由貿易協定で、日本・タイを含む15か国が加盟しています。日タイ間ではEPAに加え、RCEPも選択肢として活用できるようになりました。特徴として、原産地規則が柔軟で、複数国から部品を調達する製品でも優遇関税が適用されやすくなっています。また、RCEPを使うことでEPAではカバーされていなかった品目にも関税削減の恩恵を受けられる場合があります。利用には「フォームRCEP」による原産地証明が必要です。
ASEAN協定・特恵関税(GSP・CEPT・GSTP・AISP)
- タイはASEAN(東南アジア諸国連合)の一員であり、ASEAN域内での貿易を促進するための協定にも参加しています。
- CEPT(共通実効特恵関税):ASEAN域内での関税を低減・撤廃するための制度です。
- GSP(一般特恵関税制度):発展途上国からの輸入に対して関税上の優遇を与える制度で、タイも恩恵を受けることがあります。
- GSTP(世界的貿易特恵関税制度): 国際的な特恵関税制度です。
- AISP(ASEAN特恵統合システム):ASEAN加盟国間の特恵関税に関するシステムです。
これらの協定は複雑ですが、条件を満たせば関税を抑えることができます。
対日輸入適用税率とは何か?
「対日輸入適用税率」とは、タイが日本からの輸入品に対して適用する関税率のことです。これは、タイが世界貿易機関(WTO)に約束している「約束税率」や、前述した日タイEPAなどの経済連携協定によって定められる「協定税率」など、複数の税率の中から最も低いものが適用されるのが一般的です。どの税率が適用されるかは、商品のHSコードや原産地証明の有無によって異なります。正確な適用税率を把握するためには、最新の情報を確認することが不可欠です。
タイ輸出のメリットと注目される理由
タイへの輸出を検討されている皆様にとって、なぜ今タイが注目されているのか、その理由をご存知でしょうか?ここでは、その主な理由を3つご紹介します。
ASEANのハブとしての優位性
タイはASEAN諸国の中心に位置し、陸路・海路・空路すべてにおいて物流ネットワークが整っています。ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーといった周辺国へのアクセスが容易な地理的優位性を持っています。整備された物流網を活用すれば、タイを拠点にASEAN全域への事業展開も視野に入れられます。
外資系優遇制度(BOI、EECなど)
タイ政府は、外国企業の進出を後押しするためにBOI(タイ投資委員会)による税制優遇や、EEC内での輸出入関税免除などの優遇策を提供しています。これにより、一定条件を満たせば法人税や輸入関税が大幅に軽減されることもあり、コスト競争力を高めやすい環境が整っています。
日本製品への信頼と市場ニーズ
タイでは「日本製=高品質」というイメージが定着しており、自動車部品、機械、医療機器、食品など幅広い分野で日本製品への信頼が高まっています。中間層の拡大に伴い、品質志向の商品へのニーズも増加傾向にあり、日本企業にとっては大きなビジネスチャンスとなっています。
タイへの輸出でかかる関税コストと負担
小口貨物(1500バーツ以下)の関税免除条件
タイでは航空便や郵便で送られる小口貨物に対して、課税価格が1,500バーツ以下であれば関税が免除される制度があります。これは個人輸入など少額取引を対象にした措置ですが、ビジネス用途であっても一部の輸出に活用できる場合があります。ただし、複数の荷物を分けて送る“分割発送”とみなされると免除対象外となるため注意が必要です。
通常関税率と税負担の全体像
タイの関税率は品目によって異なりますが、平均で5〜30%程度が一般的です。これに加えて、VAT(付加価値税)7%や物品税が課される場合もあります。たとえば、家電製品や化粧品などは関税率が比較的高めに設定されている一方、原材料や一部の工業部品は無税または低税率の場合もあります。最終的な税負担額は「CIF価格+関税+その他税」で構成されるため、事前に正確な試算が重要です。
輸出側と輸入側、どちらが関税を負担するか?
通常、関税は輸入者側(タイ側)が支払うものですが、契約条件(インコタームズ)によっては輸出者側が関税や輸入税の負担を求められることもあります。「DDP(関税込み持込渡し)」条件では、関税やVATも輸出者が負担するため、利益率に大きく影響します。タイの実務に精通した上で契約内容を慎重に決定することが、トラブル回避と利益確保につながります。
輸出時に注意すべき関税・規制リスク
輸出規制品目と手続き
タイへの輸出では、品目によっては日本またはタイ側で輸出入が規制されている場合があります。化学製品や医薬品、軍事転用可能な部材などは、経済産業省や輸出管理当局への事前申請が必要です。また、タイ側でも一部の機械類や食品に対しては輸入ライセンスの取得が求められています。対象品目を事前に確認し、必要な手続きを踏むことでトラブルを未然に防ぐことができます。
タイの輸入規制(動植物検疫・ライセンス)
食品、農産物、木製品などを輸出する場合は、タイ側の検疫制度に注意が必要です。動植物検疫では、害虫・病原菌の持ち込みを防ぐため、輸出前に検査証明書(Phyto Certificate、Health Certificate)を取得する必要があります。また、タイでは一部の製品に輸入ライセンスを課しており、現地の輸入者が取得済みかどうかの確認も大切です。ちなみに木材を使用したの家具は対象です。
輸出時のVAT(付加価値税)の扱い
日本からの輸出取引では、通常「輸出免税」の扱いとなり、消費税(VAT)の課税対象外です。しかし、免税を適用するには「輸出証明書類」の整備が不可欠です。一方、タイに到着後は現地輸入者が7%のVATを支払う必要があるため、価格交渉時に税負担をどちらが持つかも明確にしておくと安心です。VATは関税とあわせて納税されるため、通関時の金額計算にも注意が必要です。
タイへの輸出手続きと必要書類のチェックリスト
輸出契約から通関・納品までの流れ
タイ向け輸出の一連の流れは、以下のようになります。
- 取引先との契約締結(インコタームズや支払条件の確認)
- 輸送手段(海上・航空)の決定と手配
- 必要書類の準備
- 日本側での輸出通関
- タイ側での輸入通関と関税・VATの支払い
- 現地配送・納品完了
必須書類(Invoice・B/L・原産地証明など)の準備ポイント
以下が主な輸出時に必要な書類です。すべて英語またはタイ語での記載が推奨されます。
- インボイス(Invoice):商品の明細・金額を記載した請求書
- パッキングリスト(Packing List):梱包内容や重量、数量の明細
- 船荷証券(B/L)または航空運送状(AWB):輸送手段の証明書類
- 原産地証明書(C/O):特恵関税やEPAを利用する際に必要
- 検査証明・成分証明書など:食品や化粧品など特定品目に必要な書類
これらの書類の不備は通関遅延の原因となるため、事前チェックが不可欠です。
通関業者との連携や不備防止の実務ノウハウ
タイへの輸出では、関税や輸入規制に関する知識だけでなく、現地通関業者とのスムーズな連携が大切です。初めて輸出する企業にとっては、書類の不備やHSコードの誤分類などによるトラブルが起こりやすく、信頼できる通関業者と協力することでリスクを大幅に軽減できます。
タイでは、通関は基本的に現地登録の通関業者(Customs Broker)を通じて行うのが一般的です。彼らは、以下のような専門サポートを提供してくれます。
- 税関とのタイ語対応(トラブル時の通訳含む)
- HSコードの正確な分類・関税率の照会
- 事前教示制度(Advance Ruling)の申請代行
- ライセンスや検疫の確認・取得サポート
また、実務でよく起こるトラブル例としては以下が挙げられます:
- インボイスとパッキングリストの記載内容が一致していない
- 船荷証券(B/L)に誤記があり、通関で荷物が保留になる
- C/O(原産地証明書)の形式ミスや記載漏れでFTAが適用されない
- 規制品目なのに輸入ライセンス未取得で通関拒否
こうしたトラブルを防ぐには、出荷前に通関業者と「書類のすり合わせ」を行い、チェックリスト形式で確認する体制をつくることが非常に効果的です。とくにEPAやRCEPを利用する場合は、原産地証明の細かな要件(品目別・フォーム別)にも要注意です。
当社では、商材別に実績のある信頼できる通関業者をご紹介できるほか、書類の事前レビュー、原産地証明の取得支援、現地とのタイ語対応支援も行っています。
「通関で止められない」「納期遅延を防ぎたい」とお考えの企業様は、ぜひご相談ください。
まとめ
タイへの輸出では、関税やVAT、輸出入規制など、細かい制度や手続きの理解が必要です。とくに初めてタイと取引する企業にとっては、「どこから始めればいいかわからない」「タイ語や関税制度に不安がある」と感じる場面も多いのではないでしょうか?
関税調査、FTA活用、通関実務までワンストップ支援します。
✅ タイ向け関税調査・書類作成のサポート
✅ 現地通関業者・パートナー企業の紹介
✅ 商談支援・販路開拓の実務代行
「タイに商品を売りたいけれど、関税や手続きでつまずきたくない」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。



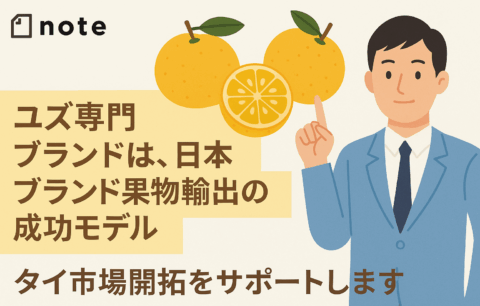

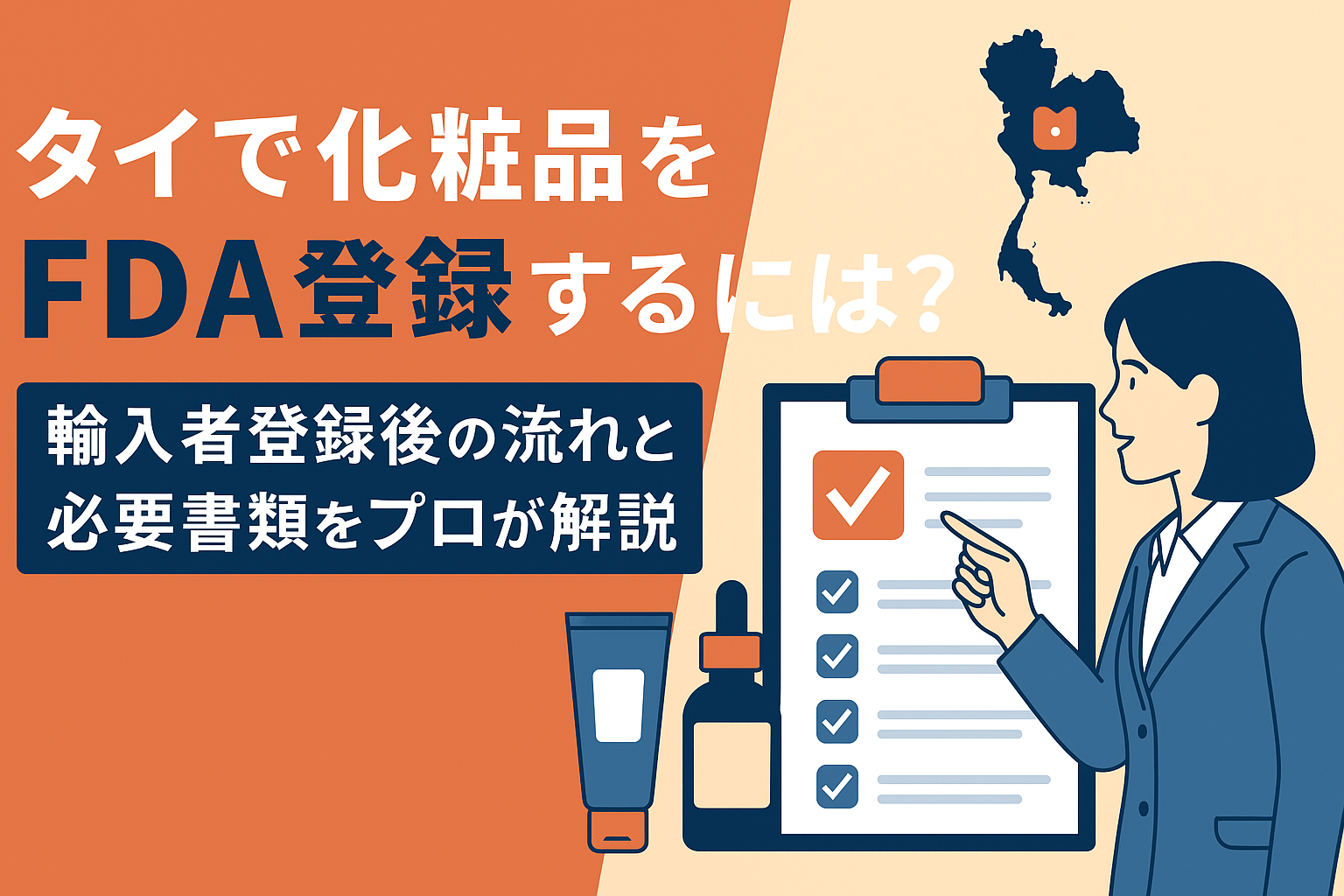


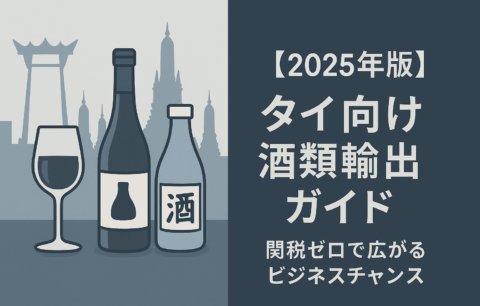
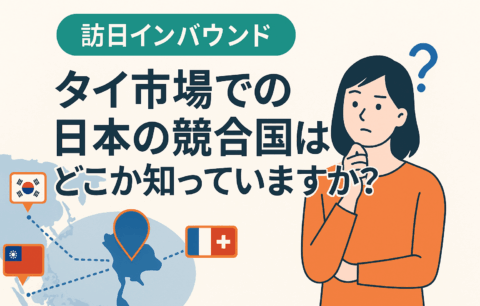

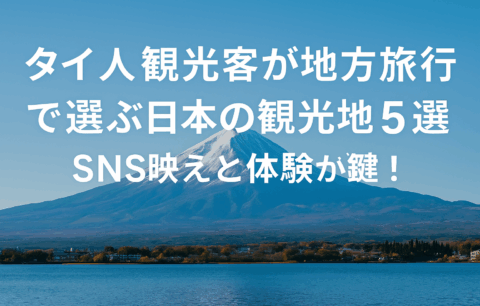


コメント