訪日インバウンドで「タイ市場の競合国」はどこの国か知っていますか?
タイ人観光客は日本への親近感が高い一方で「韓国」「ベトナム」「ヨーロッパ」など選択肢が年々増えています。「本当は日本に行きたいけれど、他の国を選んだ」という声も少なくありません。今後、日本がタイ人に「選ばれ続ける国」であるためには、競合国の強みを知り、確実に差別化する視点が欠かせません。18年間タイに住み、日本でインバウンドサービスをした筆者の視点でタイ人観光客の動向を踏まえ、日本の立ち位置と勝てるポイントを読み解きます。
タイ市場におけるインバウンドの基本と日本の立ち位置
このパートではタイ人観光客から見た日本という国を見ましょう。
インバウンドとは?|タイからの訪日旅行者の意味と役割
インバウンドとは海外から日本を訪れる外国人旅行者のことを指し、観光業界では重要な収入源となっています。タイからの旅行者は、日本の四季や文化に強い関心を持ち、リピーター率も高い傾向にあります。2023年には約99万人のタイ人が訪日しており(日本政府観光局 JNTO 調べ)、東南アジア諸国の中でも存在感は際立っています。日本にとってタイ市場は、単なる「観光客」ではなく、継続的に日本を選んでくれる潜在的なファン層とも言えるのです。
タイ人にとって「日本旅行」とはどういう存在か?
タイ人にとっての日本旅行は「憧れと特別感」のある体験です。桜や紅葉、温泉、雪景色など、タイでは味わえない自然や四季に魅力を感じている方が多く見られます。清潔な街並みや安全な交通環境、親切な接客なども高く評価されています。 一方で最近では「日本に行きたいけど、予算が合わないから韓国に行く」という声もよく聞かれるようになりました。実際、私自身がタイ人と話していても「今の日本はホテルも航空券も高いから、今回は韓国にした」という言葉を何度も耳にしています。韓国は近くて物価も安く、K-POPや韓国グルメといった文化的魅力もあり、タイの若年層を中心に人気が高まっています。このように日本は「行きたい国」であり続けている一方で、費用や予約の取りにくさが選択を左右する現実も無視できません。
なぜ訪日観光市場は今も重要視されているのか?
日本政府は「観光立国」を掲げ、インバウンド需要を中長期的な経済成長の柱としています。タイはビザ免除対象国であり、LCCを含めた航空便の拡充によりアクセスも良好です。円安の影響で相対的に日本旅行のコストが抑えられていることから、再び注目度が高まっています。こうした中で、タイ市場における日本の立ち位置を理解し、的確な施策を講じることが、観光地・自治体・企業にとって大きな成果に直結します。競合国との差別化が求められる今こそ、タイ市場の現状と未来を再確認すべきタイミングです。
なぜ「競合国」を知ることが重要なのか?
タイ人旅行者の選択肢に“韓国・台湾・欧州”がある理由
現在のタイ人旅行者にとって、日本は「行きたい国」であり続けている一方で、競合国も魅力的な選択肢として台頭しています。LCC(格安航空)の充実により、韓国や台湾、ヨーロッパなども現実的な旅行先として定着してきました。 韓国は、フライト時間が短く旅費も抑えられ、K-POPや韓国グルメといった文化的要素も相まって、若年層を中心に圧倒的な人気を集めています。台湾は、まだ訪問数という意味ではそこまで多くありませんが、官民連携での積極的なプロモーションが進んでおり、今後の伸びが期待される市場です。実際、バンコク市内のBTS(スカイトレイン)車内では、台湾旅行を訴求する広告が掲載されており、視認性の高い交通媒体を使って印象づけに取り組んでいます。
ヨーロッパにおいてはスイスが注目されています。雪山リゾートを中心とした“映え”と“非日常体験”を軸に、ハネムーンや記念旅行層をターゲットとしたマーケティングが展開されており、同じくバンコクのBTS車内でスイスの雄大な雪山の写真を使った広告が目立っていました。
このように各国が現地目線でタイ人の心をつかむ戦略を仕掛けていることから、日本も「ただ人気がある」だけでは選ばれ続けるのは難しくなっています。競合国の動きを正確に把握し、自国との違いを見極めることが今後の鍵となります。
「行きたいけど行けない日本」の背景とは?
日本は今もなお、タイ人にとって「行きたい国」の上位に位置しています。しかし、実際の行動に結びつかないケースも少なくありません。私自身、タイ現地でのやり取りの中で「本当は日本に行きたいけれど、航空券や宿泊費が高すぎるので今回は韓国にした」という声を頻繁に聞きました。2024年以降は円安の恩恵も限定的となり、ホテル不足や物価高、予約の取りにくさなどがタイ人旅行者の心理的ハードルになっています。短期間で満足度の高い旅行をしたいというニーズが高まっているため、時間的・金銭的な効率を重視する動きも影響しています。こうした「選ばれない理由」に真摯に向き合うことが日本再選択への第一歩となります。
競合国を知ることで見える、日本の課題と可能性
競合国の魅力や戦略を知ることは、自国の課題と改善ポイントを客観的に見直す大きなヒントになります。韓国ではK-カルチャーを活用した統一感のあるプロモーションが国全体で展開されており、空港や市街地でのSNS拡散設計も徹底されています。一方、日本は地方観光資源が豊富で「四季」「食文化」「安全」といった強みがあるものの、それらが一貫性を持って伝わっていないのが現状です。競合との差を知ることで日本ならではの魅力をどう再構築するかが見えてきます。競合を正しく理解し、差別化と共感の戦略を練ることが、今後の訪日誘致成功のカギになります。
タイ人観光客を受け入れるメリットとリスク
地域経済・文化交流にもたらす好循環
タイ人観光客は比較的長期滞在傾向があり、地方都市での消費意欲も高いことから観光地周辺の飲食・宿泊・体験産業に大きな経済効果をもたらします。タイ人は親日的で礼儀正しく、現地の文化に敬意を払う傾向があるため、地域住民との交流や国際理解の促進にもつながります。タイのSNS拡散力は強く、旅先での体験がそのまま次の来訪者を呼ぶ「感動の連鎖」が期待できます。インバウンドを単なる経済効果にとどめず、地域資源の価値向上にも活かせる存在として捉えることが大切です。
観光地の混雑・対応課題(予約・言語・物価)
一方で、受け入れ体制の整備が追いついていない観光地では混雑や予約困難といった課題も浮き彫りになっています。タイ人旅行者からは「人気施設のチケットが取れない」「英語やタイ語での案内が少ない」といった声が寄せられています。こうした背景から日本側の情報発信や言語対応、柔軟な予約システムなどを改善しなければ、せっかくの興味が他国へ流れてしまう可能性もあります。
“価格で選ばれない”観光地になるための工夫
「安いから行く」のではなく「そこにしかない体験があるから行く」──この価値を提供できるかが、日本の地方観光地に問われています。タイ人旅行者にとって、価格だけでなく“特別感”“写真映え”“文化的な深み”といった要素が重要な判断基準です。そのためには、地元ガイドによるストーリーテリングや季節限定の体験コンテンツ、SNSでシェアしたくなる演出などが効果的です。価格競争に陥らず“心に残る旅先”として選ばれるための工夫が求められています。
タイ人のリアルな選択肢|競合国と日本の比較
韓国:近くて安い+K-カルチャーの強み
韓国は現在、タイ人旅行者にとって人気のある旅行先です。その理由は明確で、飛行時間は約5時間以内と近いながら、LCCを含め航空券も手頃です。物価も日本に比べて抑えられており、食事や宿泊、ショッピングすべてにおいて“コスパの良さ”が魅力となっています。さらにK-POP、韓国ドラマ、ファッション、美容といったK-カルチャーがタイの若年層を中心に大きな影響力を持っており、「推し活」を目的とした旅行者も少なくありません。韓国はSNS映えやオリジナル体験を意識した観光コンテンツの開発にも力を入れており、満足度の高い滞在体験を提供しています。
ベトナム:親しみやすく費用も抑えられる“手軽な旅”
ベトナムは価格重視の旅行者にとって「手軽に行けて安心できる」選択肢として存在感を強めています。ベトナムは歴史的背景や文化的共通点から、タイ人にとって馴染みやすく、なおかつ費用が抑えられるため、グループ旅行や短期旅行先として選ばれています。タイ人からはベトナム料理がおいしいという声も多いです。
フランス・スイス:ハネムーン層に選ばれる“映えとブランド”
タイでは“人生の節目にはヨーロッパ”という憧れが根強く、フランスやスイスはハネムーン先として高い人気を誇ります。バンコクのBTS車内では、スイスの雪山を背景にした大型ビジュアルが掲出され、視覚的なインパクトで「非日常の旅」への期待感を高めています。こうしたラグジュアリーでフォトジェニックな国々は「一生に一度の体験をしたい」と考える層に訴求しやすく、SNSでも高い拡散力を持ちます。スイスは四季を通じた自然美や高級感のある滞在体験を武器に価格以上の価値を感じさせる戦略で存在感を発揮しています。スイスのあの大自然は日本人でも憧れますよね。
なぜ“日本じゃなくてもいい”という声が増えつつあるのか?
かつては「行くなら日本一択」とされていたタイ人旅行者の選択肢は、今や多様化しています。「日本は大好きだけど、ホテルが高くて予約も取りにくいから、今回は韓国にした」「行ったことがあるから、次は他の国を試してみたい」など、実際に現地でこうした声を頻繁に聞くようになりました。この背景には、物価高や混雑、情報不足といった“行きづらさ”と、競合国の積極的なプロモーションがあります。各国が現地マーケットに合わせた戦略を展開する中で、日本がこれまでの「人気先進国」の立場に甘んじることなく、再び“選ばれる理由”を再構築していく必要があります。競合のリアルな存在を認識することが、次の一手を見出すヒントとなるのです。
日本が“選ばれる理由”を再定義するプロモーション戦略
SNS・KOL活用で“行きたくなる理由”を再設計する
タイ市場においてはSNSやKOL(インフルエンサー)の影響力が旅行先の選定に大きく作用します。InstagramやTikTokでの“映え”を意識した投稿は、旅の目的そのものをつくり出す起点になります。日本の観光地でも、美しい自然や伝統文化が強みでありながら、それをどう表現し、どう届けるかによって集客効果が大きく変わります。 私自身、タイ人KOLとの交渉や現地でのタイ語SNS運用支援を通じて、彼らが求めているのは「体験価値+拡散価値」であると感じています。浴衣体験やローカル市場の紹介などは、日本にしかない魅力でありつつ、フォロワーに“見せたくなる”要素を備えています。SNS発信とプロモーションを一体で設計することで「日本に行きたい」という気持ちを自然に引き出すことが可能です。
映え・体験・季節性で“唯一無二の価値”を届ける
韓国などの競合国と差別化するためには「日本ならでは」の魅力を再編集して伝える必要があります。なかでも重要なのは、以下の3つの要素です。
- 映え(視覚的インパクト):桜、雪景色、紅葉、和の建築など、視覚的に美しいロケーションを活用し、撮影スポットとして情報発信する。
- 体験(参加型コンテンツ):着物体験、陶芸、和菓子づくり、地元食体験など、「見るだけでなく、やってみたい」と思わせるアクティビティを用意する。(浅草のお守りつくりはタイ人にとても喜ばれました!)
- 季節性(旬の魅力):季節ごとの自然や祭り、地域行事などを通じて、「今行く理由」を訴求する。
これらをKOLや旅行メディアと連携して発信することで、“選ばれる観光地”としての価値を確立できます。
「2回目の日本旅行」の設計が鍵になる
現在、日本へのリピーターが増えている一方で「どこへ行くか分からない」「同じところしか紹介されていない」といった声もあります。初回訪問では東京・大阪・京都の“ゴールデンルート”が定番ですが、2回目以降はよりパーソナルな体験や地方の魅力が求められる傾向にあります。
- スキーや雪遊び体験(北海道・長野)
- ローカル温泉と伝統宿(東北・九州)
- 農業・漁業体験や伝統工芸見学(中部・四国)
こうしたテーマ性のある地域旅を提案することで消費単価の向上や滞在日数の延長も期待できます。単なる「再訪」ではなく「テーマ型再発見」を促すプロモーションが、訪日インバウンドの新たな扉を開く鍵となるでしょう。
タイ人観光客の“不安・不満”を解消する視点
情報不足・言語対応・予約の壁への対応策
「行きたいけど情報がない」「予約の仕方がわからない」といった声が依然として多くあります。現地発の旅行予約サイトでは日本の宿泊施設や体験が掲載されていないケースも多く、選択肢が狭まってしまいます。こうした壁を取り払うには、タイ語対応の公式WebページやSNS、オンライン予約プラットフォームとの連携が欠かせません。タイ人スタッフの起用やLINEやFacebookなどタイ人が慣れ親しんでいるチャネルでの問い合わせ対応も効果的です。
「行ったら残念」にならないための現場づくり
「期待していたのに、現地でがっかりした」という体験はリピート意欲を大きく下げてしまいます。SNSで見た“映えスポット”がメンテナンス不足だった、スタッフが外国人対応に慣れていなかった、説明が通じず困った…など細かなストレスが旅行体験全体に影響を与えます。こうした課題を防ぐには、現場スタッフへのインバウンド研修や多言語ピクトグラムの整備、簡易な翻訳ツールの設置など基本的な“おもてなし力”の底上げが不可欠です。
観光地と旅マッチングのズレをなくす工夫
インスタで人気の場所に行ったものの交通が不便で滞在時間が短かった、期待していた体験が事前予約制で参加できなかった、などのズレです。これを解消するには、事前に「誰に、何が、どう伝わるか」を意識した旅の導線設計が大切です。タイ人が重視するのは、“手軽さ”“安心感”“シェアしたくなる価値”です。その視点での情報設計や体験導入が満足度向上とSNSでの拡散につながります。
タイ市場を狙うためのマーケティング&調査の進め方
リピーター率・旅行動機・支出傾向の分析
タイ人訪日客のリピーター率は比較的高く、観光庁のデータでも約60%以上が「2回以上訪日経験あり」と報告されています。初回訪問者とリピーターでは旅行動機や消費行動が異なるため、戦略も変える必要があります。初回は「東京・京都・大阪」が主流ですが、リピーターは地方の自然や文化体験、温泉などに興味を持ちやすい傾向があります。支出面でもリピーターほど“モノ”より“体験”に価値を感じる傾向が強くなっており、この行動特性に合わせた商品設計が求められます。
SNSのハッシュタグ・投稿傾向から見る興味の変化
InstagramやTikTokなどSNS上でのタイ人ユーザーの投稿傾向を見ると、「#JapanTrip」「#เที่ยวญี่ปุ่น」(日本旅行)などのハッシュタグが依然として人気です。しかし近年では「#Onsen」「#KimonoExperience」「#SnowInJapan」など“体験型”・“季節感”のある内容が多くなってきています。また「#ญี่ปุ่นครั้งที่2(2回目の日本)」のように、リピーターを意識したタグも見受けられます。SNSの投稿内容からは旅の目的が「観光地を見る」から「特別な体験をする」へと変化していることが読み取れます。ハッシュタグ分析を通じて、マーケティングの方向性を可視化しましょう。
韓国・台湾など他国のプロモーション事例と比較
競合国である韓国は現地での情報発信力を高める戦略を実施しています。韓国はK-カルチャーと連動させたパッケージツアーや韓国政府観光公社によるYouTubeキャンペーンが強く、現地のSNSトレンドにも即した内容です。これに対し、日本のタイ市場向け施策は情報の「分散」や「言語対応の弱さ」が課題とされており、競合の成功例を分析し、自社エリアや施設でどう落とし込むかが重要です。
タイ市場向けインバウンド施策に役立つ支援・ツール紹介
KOL連携・SNS施策での成功事例(スキー・着物・温泉体験など)
タイ市場ではKOL(インフルエンサー)との連携が大事です。スキー体験や着物レンタル、温泉旅館滞在などをテーマにした招待施策ではSNSでの拡散効果により予約数やフォロワー数が大きく伸びた事例が多数あります。タイ人KOLが北海道での雪遊びや東北の露天風呂を紹介した動画は100万回以上再生されたケースもあります。KOLと連携することで現地語で“体験の温度感”をリアルに伝えることができ、日本への関心を行動につなげることが可能です。
地方自治体・DMOが取り組めるスモールスタート支援策
地方自治体やDMO(観光地域づくり法人)にとって、タイ市場向け施策は「大きな予算が必要」と感じられがちですが、実はスモールスタートで実行できる方法も数多くあります。少人数KOLのモニターツアーやタイ語でのSNS開設、現地旅行会社とのタイアップ商品開発など、費用対効果の高い取り組みが可能です。観光庁やJETRO、自治体向けの海外プロモーション助成金などを活用すれば、コストを抑えて実施できる選択肢も広がります。
費用を抑えて効果を出すプロモーション構築のポイント
限られた予算でもタイ市場で効果を出すには、以下のような“現地目線”を取り入れることが重要です。
- タイ語ネイティブによるSNS運用や動画字幕の導入
- 1万人未満でもエンゲージの高い「マイクロKOL」の活用
- LINE、Facebookなどタイで主流の媒体への広告出稿
- 日本在住のタイ人留学生・労働者との情報発信協力
これらを段階的に組み合わせることで過度なコストをかけずに継続的な接点を生み出すプロモーション体制を構築できます。現地感覚と専門性を兼ね備えたパートナーとの連携が、最も効率的な第一歩となります。
タイ市場で成果を出すために
タイ人観光客のニーズや競合国の動向を正しく捉えることで、訪日インバウンドの成果は大きく変わります。
「何から始めればいいか分からない」
「KOLとプロモーションをしてみたい」
そんな方へ向けて、無料相談を実施中です。
お気軽にご連絡ください。
タイ市場での第一歩を、共に築いていきましょう!


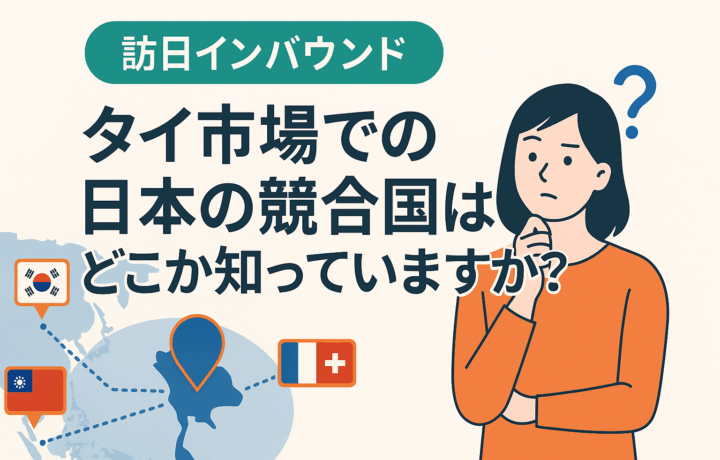


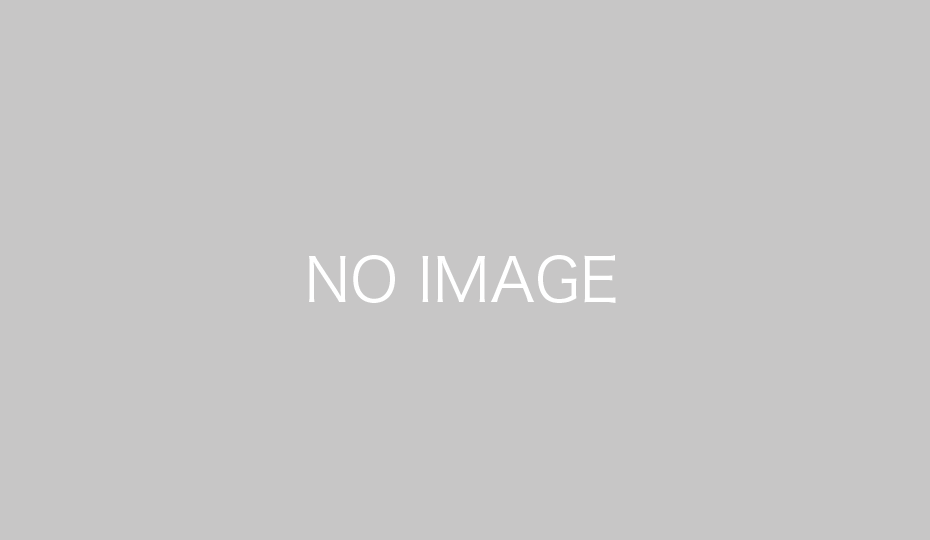


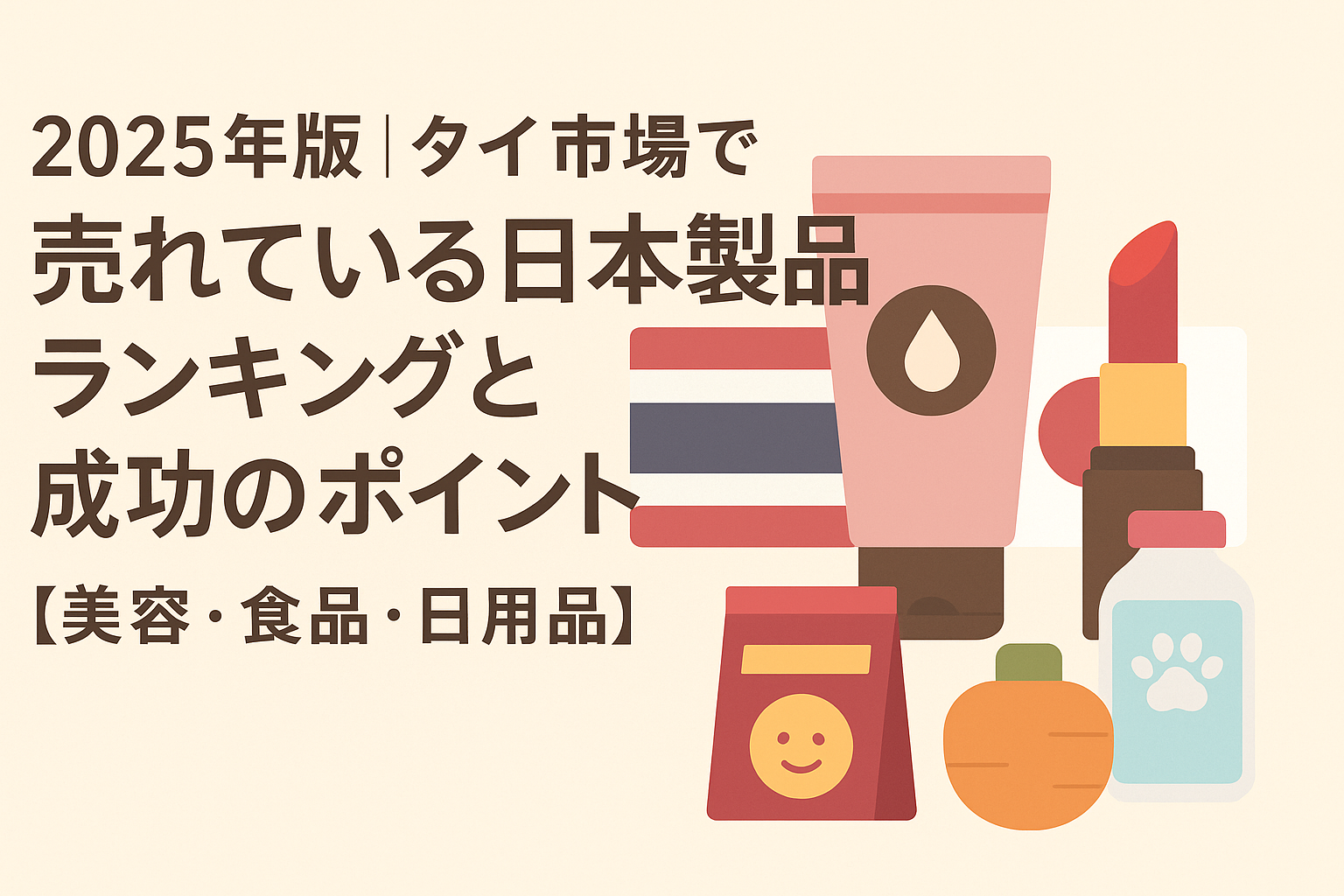




コメント