東南アジア市場、タイへの酒類輸出に関心をお持ちの方へ朗報です。2024年からタイではワインなど一部酒類の関税がゼロになり、日本の中小酒造メーカーにとって新たな商機が広がっています。しかし、実際に輸出を進めるには、税制変更だけでなく、輸入許可や書類対応、FDA登録の要否など、細かい実務を理解しておく必要があります。本記事では、タイ在住18年・商社出身の筆者が制度変更の要点から輸出フロー、注意点までをわかりやすく解説します。
タイで酒類関税がゼロに!|最新税制改革の概要と背景
2024年からの関税撤廃と税制緩和(ワイン・スピリッツなど)
2024年2月、タイ政府は酒類に関する税制の大幅な見直しを行い、ワイン(HSコード2204・2205)など一部の酒類に対して課されていた関税を完全に撤廃しました。これにより従来54〜60%とされていたワインの輸入関税が0%となり、日本からの輸出にかかるコストが大きく削減されました。同時にスピリッツなどの国内生産酒類に対してもエキサイズ税の引き下げが実施され、税負担の軽減が図られています。
この改革はタイ国内の観光・飲食業界の回復支援や国際的な流通の活性化を目的としたもので、日本の中小酒造メーカーにとっては新たな輸出機会となる好材料です。これまでコストの壁が高く、タイ進出を見送っていた事業者にとって、いまが進出の絶好のタイミングといえるでしょう。
販売価格に対する課税の一律化(5%へ)
さらに今回の制度変更では販売価格に対して課されるad valorem税(付加価値税的なもの)も見直されました。従来は販売価格1,000バーツ未満の商品には0%、1,000バーツ以上には10%の課税がなされていましたが、これが一律5%に統一されました。
この変更により高価格帯の商品にとっては実質的な減税となり、高級日本酒やプレミアムワインといった商品の価格競争力が高まりました。反対に低価格帯商品はこれまで非課税だったため、若干のコスト増になりますが、それでも関税撤廃の効果が上回るため、全体としてはポジティブな改定といえます。
政府の狙いと輸入環境の変化
今回の税制改革の背景には観光復興に向けた取り組みや消費促進、合法的な流通の整備といった政府の複合的な狙いがあります。観光大国タイでは外食やエンタメ業界の復活が経済の鍵とされており、酒類市場の活性化はその一環として位置付けられています。
輸入業者にとっても、制度が簡素化されたことで申請や通関の手間が軽減される傾向にあります。正規輸入ライセンス保持者を通すことで必要書類の作成や税金計算などがスムーズに進むケースが増えています。
このように、制度面・実務面の両方からタイへの酒類輸出がしやすくなっている今、タイ市場への参入を検討する価値はますます高まっています。
どんなお酒が対象?|関税ゼロの酒類と対象外商品の違い
ワイン(HSコード 2204, 2205)
2024年の税制改正により、タイではワイン(HSコード2204および2205)にかかる輸入関税が完全撤廃されました。対象となるのは、ぶどうを原料とした静置ワインや発泡ワインなどで日本国内のワイナリーからタイ市場に向けた販路開拓が一気に現実味を帯びています。
ただし、関税が撤廃されても、他の税金(エキサイズ税やVAT)は別途課税されるため、トータルのコスト構造は正確に把握しておく必要があります。プレミアムワインなど高価格帯の商品は今回の改定によってより競争力のある価格で提供できるようになりました。
焼酎、日本酒、ウイスキーなどの対応状況
ワイン以外の酒類、たとえば焼酎、日本酒、ウイスキーに関しては、現時点では輸入関税の完全撤廃はされていません。ただし、FTA(自由貿易協定)に基づく段階的な税率引き下げが進められており、将来的には関税ゼロとなる可能性もあります。
日本酒はFTAの対象品目となっており、協定の年次スケジュールに基づいて税率が毎年削減されています。現在の関税率は20%以下にまで下がっており、一定の価格帯であればすでに十分な競争力があります。また、ウイスキーについても特定の条件下で関税優遇が適用されるケースがあるため、HSコードごとの確認が重要です。
税金以外にかかる費用(エキサイズ税、VATなど)
関税が撤廃されても輸入時には以下の税金が引き続き課税されます。
- エキサイズ税(特別消費税):アルコール度数および容量に応じて課される税金。ワインは100%ABV換算で1,000バーツ/リットル程度。
- ad valorem税:2024年の改定により、販売価格に関係なく一律5%となりました。
- 付加価値税(VAT):現在7%。他の税金と合算して計算されます。
これらを合算すると実際の販売価格に対する課税負担は依然として存在しますが、関税撤廃のインパクトにより全体としてはコストが軽減されています。輸出計画の立案時には、これらの費用を含めた収支シミュレーションが必要です。初めての輸出の場合は、現地パートナーとの綿密な連携が不可欠です。
タイへのお酒輸出の基本フロー|準備〜輸送・通関まで
STEP①:輸出者側で準備すべき書類(インボイス、成分表等)
日本からタイへお酒を輸出するには、まず輸出者側で必要な書類を整えることが第一ステップです。以下は基本的な必要書類の一覧です。
- インボイス(Invoice):商品の品名、数量、単価、合計金額などを記載
- パッキングリスト(Packing List):商品ごとの梱包明細
- 成分表(Certificate of Ingredients):アルコール度数、原材料などの情報を明記
- 製造者証明書(Manufacturer Certificate):日本酒やワインの場合、製造元の証明書が求められることがあります
- ラベルのサンプル画像(販売用の場合)
これらは輸入者が通関・登録を行う際に必要となるため、事前に揃えておくことが大切です。成分表とラベル情報はFDA登録や通関時に使用されるため、内容に不備がないよう注意が必要です。
STEP②:輸入者側が行う手続き
タイ側の輸入者には、酒税局の輸入ライセンス(販売・非販売用で異なる)が求められます。試飲用や展示会用のサンプル輸入ではFDA登録は不要でも「酒税局の輸入許可」は必須です。
必要となる書類例:
- 酒税局提出用の申請書(Por Sor. 08-01)
- 登記簿謄本(Company Certificate)
- 代表者IDコピー
- インボイス・成分表
- 委任状(代理申請する場合)
- 税金の計算ファイル(Excel形式)
輸入者はこれらの書類をドラフトの形でまずメールで酒税局に提出し、確認を得た後に原本を提出して輸入ライセンスを取得します。申請から許可発行まではおよそ2週間前後が目安です。
STEP③:FDA登録/ラベルのタイ語表記義務
輸入されたお酒が商業販売目的である場合は、タイ食品医薬品局(FDA)への登録が必要です。ワイン・日本酒・焼酎などの酒類はタイ語でのラベル表記が法律で義務付けられています。
ラベルには以下の内容を記載する必要があります:
- 商品名(タイ語・英語)
- 成分・アルコール度数
- 内容量・製造日・賞味期限
- 輸入業者の情報(社名・住所・電話番号)
- FDA認可番号
登録には現物サンプルや成分表が必要で通常2〜4週間程度の期間を要します。輸出スケジュールを立てる際にはこの期間を必ず考慮しましょう。
FDA登録に関してはこちらの記事をご参照ください。
STEP④:輸送と通関(フォワーダーの選定など)
輸送手段としては少量であれば空輸、大量の場合は海上輸送が一般的です。輸送時には温度管理が重要となるため、ワインや日本酒はリーファーコンテナの利用がおすすめです。
通関手続きに関しては、信頼できるフォワーダー(物流会社)を選ぶことで書類不備による遅延やトラブルを避けることができます。フォワーダーは、税関申告、配送調整、納品管理まで一貫して対応してくれるため、初めて輸出を行う方にとっては大きな支えになります。
フォワーダーの選定時は以下を確認しましょう:
- 酒類輸送の実績があるか
- タイ側のパートナーがしっかりしているか
- 小ロット対応可否
Withthaiでは、こうしたフォワーダーの選定や通関アドバイスも含め、輸出支援を行っています。初めての輸出で不安がある方も、安心して取り組める体制を整えています。
輸出に関する記事はこちらも参照ください。
よくあるトラブルと対策|通関・税務・ラベル不備 etc.
関税ゼロでも書類不備で通関NGに
タイでの関税がゼロになったとはいえ、輸入手続きそのものが簡素化されたわけではありません。むしろ、税率が下がった分、書類の正確性や税務申告の整合性に対するチェックが厳しくなっている傾向があります。
多いトラブルが輸出書類の不備による通関停止です。インボイスに記載されている商品名とラベル表示や成分表との内容に齟齬があると、タイの税関では疑義を持たれやすく、審査に時間がかかってしまいます。
また、インボイスの記載漏れや誤訳、ラベル画像の提出忘れなども、書類不備として扱われることがあります。これらは防げるミスであるため、輸出前の二重チェックが重要です。
輸出価格と実際の仕入価格の食い違い
もうひとつの典型的なトラブルは、インボイスに記載された価格と実際に現地で販売される価格の差が大きすぎる場合です。タイの税関や税務署は、「適正価格での申告」を重視しており、著しく低い価格での輸出は脱税や価格操作とみなされることがあります。
アルコール類は税収の重要な対象であり、税率の計算に「販売価格」が使われる場面も多いため、価格の設定と説明責任は重要です。必要に応じて価格の根拠となる資料や取引実績を提出できるように準備しておくと安心です。 <h3>イベント用(販売不可)と販売用の混同</h3>
展示会や試飲会で使用する「非販売用」のお酒を輸入する場合でも、輸入許可は必要です。よくある勘違いは、「販売しないから手続きは不要」という思い込みです。しかし実際には、タイの酒税局が発行する「非販売用途の輸入ライセンス」が必要であり、これがないと通関ができません。
また、イベント用としながらも現地で一部販売してしまうと、重大な違反となり、罰則や将来的な輸入禁止措置に発展する可能性もあります。サンプル用と販売用はラベルや数量の扱いも異なるため、輸出時に明確に区別して申請する必要があります。
Withthaiでは、こうした輸入区分の見極めや、書類の正しい整備についてもサポートしております。初めての輸出で不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
タイ市場で日本のお酒が注目されている理由
富裕層・Z世代に人気の「日本ブーム」
タイではここ数年「日本ブーム」が根強く続いています。なかでも富裕層や都市部のZ世代を中心に日本の食文化やライフスタイルへの関心が高まり、その延長線上で「日本のお酒」への注目も急速に高まっています。
日本酒やワインは「品質が高くて安全」「味わいが繊細」「ラベルやパッケージが美しい」といった理由で高級レストランやホテルのメニューに採用されるケースも増加中です。また、お酒を単なる嗜好品ではなく“日本文化の象徴”として楽しむ消費者も現れています。
タイ人インフルエンサーが日本酒を紹介した投稿がSNSで拡散された例もあり、情報感度の高い層を中心に着実に市場が広がっています。
SNS映え・健康志向(抹茶系・低アル商品)
若年層を中心に「見た目の美しさ=価値」というトレンドは、飲料にも波及しています。カラフルで美しいボトルデザイン、上品な和風パッケージ、日本語ラベルなどは「インスタ映え」「TikTok映え」として評価されやすく、SNSを通じた自然な拡散にもつながっています。
健康志向の高まりも追い風です。日本の低アルコール飲料や無添加のナチュラル系ワイン、糖質オフの日本酒などは、体にやさしいイメージとあいまって注目を集めています。タイでは「体にいいお酒」というマーケティングが有効でFacebook上で医師や専門家が日本製の飲料を推奨する投稿がバズることもあります。
飲食店の日本化&観光回復
バンコクをはじめとする都市部では日本食レストランの出店が続いており、居酒屋・寿司・ラーメンなど多彩な業態がタイ人に受け入れられています。こうした店舗では日本酒や焼酎、梅酒などの取り扱いが増加傾向にあり、現地での「日本のお酒」の接触機会が日常に入り込んできています。
また、2024年以降、訪日観光の回復も進み、日本を訪れたタイ人が現地で飲んだ日本酒やクラフトビールを「お土産」として再び求める動きも見られます。これにより越境ECや現地でのリピート消費の需要が生まれており、インバウンドとアウトバウンドの相乗効果が期待できます。
日本のお酒は今、タイで確かな市場を形成しつつあります。「いま輸出する価値があるか?」という問いに対しては、明確に「はい」と言える状況です。
タイ市場で日本のお酒が注目されている理由
富裕層・Z世代に人気の「日本ブーム」
タイでは「日本ブーム」が長年続いており、富裕層や若年層の間で日本製品に対する信頼感と好感度が高まっています。その中でも日本のお酒は日本食や文化に触れる中で自然と受け入れられる存在となっており、高品質・安心・プレミアム感を兼ね備えた商品として人気を集めています。
また、旅行や留学を通じて日本に親しみを持ったタイ人が、帰国後に日本酒や梅酒を飲む機会を求めるケースも増えており、消費の裾野が広がっています。
<h3>SNS映え・健康志向(抹茶系・低アル商品)</h3>
タイのZ世代・ミレニアル層では「見た目に映える商品」が選ばれる傾向が強く、日本酒や果実酒の美しいラベルデザイン、ガラスボトルの高級感が「SNS映えする」として注目されています。InstagramやTikTokで「#ญี่ปุ่น」や「#sake」といったタグを使い、日本酒を紹介する投稿も多数見られます。
さらに健康志向の高まりにより、抹茶を使った低アルコール飲料や糖質オフの日本酒などが「ヘルシーなお酒」として支持されています。Facebook上では、医師やインフルエンサーが紹介する“身体に優しいお酒”として日本製品が紹介され、話題を集めることもあります。
飲食店の日本化&観光回復
バンコクを中心に日本食レストランの出店が続いており、居酒屋や寿司屋では日本酒や焼酎を取り扱うのが一般的になりつつあります。飲食店が“日本の雰囲気”を再現する中で、本物の日本酒を提供することが差別化につながっているのです。
訪日観光の回復により、日本で実際に飲んだお酒をタイでも探す動きが活発化しています。旅行をきっかけに日本酒の魅力に目覚めたタイ人が、帰国後に越境ECや現地販売でリピート購入する事例も増えており、インバウンドとアウトバウンドが連動する形で市場が広がっています。
【現地経験者が語る】輸出を成功させるための3つのポイント
信頼できる現地パートナーと組む
タイへのお酒輸出を成功させるうえで、現地に信頼できるパートナーがいるかどうかは極めて重要です。書類の提出先である酒税局やFDAとのやり取りは基本的にタイ語で行われるため、日本側だけで完結することは難しく、経験豊富な現地輸入者との連携が不可欠です。
酒類の輸入ライセンスを保有し、輸入実績のある企業であれば、書類の整備や輸入手続き、税務対応までスムーズに対応できます。初めて輸出する企業ほど、信頼できる現地窓口と協業することで、リスクを最小限に抑えることができます。
日本側の書類ミスを最小化
実務上もっとも多いトラブルの一つが日本側で作成する書類の不備です。インボイスの品名が成分表と一致していない、ラベルサンプルが提出されていない、原産国表示が不明瞭など、ほんのわずかなミスでも通関に支障をきたします。
タイの税関や酒税局は提出書類の正確さを重視しており、不備があると再提出や差し戻しにより時間とコストがかかってしまいます。輸出前に必ず書類チェックリストを作成し、第三者によるダブルチェックを行うことをおすすめします。
ラベル・パッケージは「魅せる」ものに
タイ市場では、商品の「第一印象」が購買に大きく影響します。ワインや日本酒などは味だけでなく見た目でも選ばれるため、ラベルやパッケージは単なる情報表示ではなく、マーケティングツールとして設計すべきです。
タイ語のラベル表示が義務付けられている中で、日本の美意識を残しながら現地消費者にとっても分かりやすく、魅力的に映るデザインにすることが求められます。また、フォントや色使いもSNS映えを意識することで、若年層への訴求力が高まります。
こうした工夫を通じて、単なる“輸出”にとどまらず、現地で“選ばれるブランド”を目指すことが、長期的な市場拡大につながります。
Withthaiの貿易サポートで、初めてでも安心
輸出書類作成・翻訳・実務をワンストップで支援
Withthaiでは日本企業がタイにお酒を輸出する際に必要なインボイス、成分表、ラベル翻訳などの書類作成をサポートしています。タイ語での行政手続きや法規制への対応にも精通しており、初めての方でも安心してご相談いただけます。
輸入者との橋渡し・現地対応も対応可能
現地輸入業者とのコミュニケーションや、酒税局・FDAとの調整もWiththaiが間に入って対応いたします。現地パートナーとの信頼関係を活かし、煩雑なやり取りを代行することで、スムーズな輸出・通関を実現します。
👉 無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。








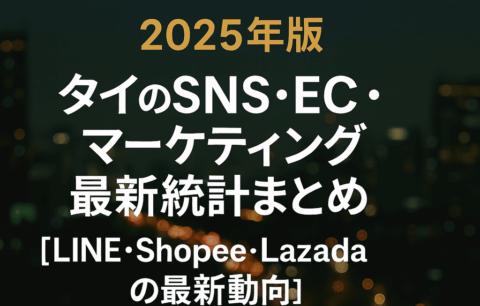
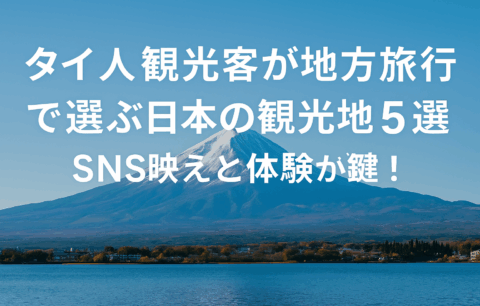

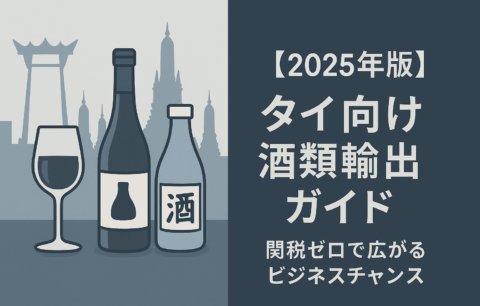


コメント