「タイに商品を輸出したいけれど、何から始めればいいのか分からない」──そんなお悩みはありませんか?本記事ではタイへの輸出を考える企業がまず知っておくべき基本手続きや必要書類、気をつけたい規制までをわかりやすく解説します。中小企業にとってハードルになりがちな通関やライセンス取得も具体的な流れに沿って紹介。実務経験に基づいた内容です。今こそ、タイ市場への一歩を踏み出しましょう。
タイ輸出って何から始めればいい?初心者がまず知るべきこと
ここでは初心者がまず押さえるべき2つのポイント、
「輸出可能性の確認」と「タイ企業との実務コミュニケーションの注意点」について実体験を交えて解説していきます。
これからタイへの販路を広げたい方は、ぜひ参考にしてください。
タイ現地とのやり取りで失敗しないためのポイント
タイ企業とビジネスを進める上では文化や商習慣の違いを理解したうえでコミュニケーションを取ることが重要です。日本では当たり前のように通じる言い回しや交渉のスタンスもタイでは誤解や遠回しな断りの原因となることがあります。以下のような点は注意が必要です。
・やり取りはタイ語または英語。翻訳精度と語調に配慮
・タイでは「NO」と明言せず曖昧に断る文化がある
・商談では丁寧かつ段階的な確認が信頼構築につながる
納期・価格・仕様に関する約束は必ず書面で交わすようにしましょう。現地事情に通じた通訳やビジネスアテンドがいるとミスを未然に防ぐことができます。初めての輸出で失敗しないためには、言語と文化に精通したパートナーの存在が不可欠です。
タイ輸出の全体フローと必要な手続きまとめ
実際の現場での経験をもとにタイ輸出に必要な4つの主要ステップをご紹介します。
ステップ1:輸出入規制の確認・契約締結
最初のステップは取り扱う商品が輸出可能かどうか、また輸入側(タイ)の規制に引っかからないかを確認することです。日本側では外為法、タイ側では各種関係省庁による輸入制限があるため、事前調査が求められます。
- 日本からの輸出規制対象品目か確認(軍事転用物資など)
- タイで輸入にライセンスや検査が必要な「管理品目」かどうか
- HSコードをもとに必要書類や関税率を確認
そのうえで現地の輸入者と売買契約を結ぶ必要があります。契約書には、商品名・数量・納期・取引条件(インコタームズ)・支払条件を明記し、輸送や通関時のトラブルを未然に防ぎます。
ステップ2:輸出入許可申請とライセンス取得
商品によっては日本またはタイ側で許可申請や登録手続きが求められます。タイ側では「E-Customs」というオンラインシステムでの登録が基本となります。E-Customsは、タイ側の輸入通関で使用されるオンライン通関システムです。このシステムでは電子署名による認証が必要であり、登録や維持には注意点があります。
E-Customsの登録と申請方法
E-Customsは、タイ財務省関税局が運営する電子通関システムです。以下の手順で利用開始できます。輸入者は登録します。
- 関税局または通関業者を通じて利用者登録
- 企業情報・担当者情報を登録し、電子署名の申請
- 承認後、通関や税関書類のやり取りが可能に
登録は原則として一度行えば継続利用が可能ですが、担当者の交代や会社情報の変更時には更新手続きが必要です。
レッドライン商品や管理品目の事前審査
タイでは「レッドライン商品」と呼ばれる厳しい管理が必要な品目が存在します。
医薬品、食品、電化製品などが該当し、該当する場合は関係省庁(例:食品医薬品局・工業省)からの事前承認が求められます。輸出前に書類が揃っていないと現地で輸入できず長期保留・追加費用が発生することもあります。
ステップ3:輸送と通関の手配(航空便・船便)
手続きが整ったら実際の輸送と通関手配に移ります。日本からタイへは下記2つの輸送方法が一般的です。
- 航空便:スピード重視。化粧品や精密機器など軽量品に向いています。
- 船便:コスト重視。大型商品や数量の多い商品に適しています。
輸送業者(フォワーダー)と連携し、インボイスやパッキングリストなどの輸出書類を作成。事前に日本側での輸出通関とタイ側での輸入通関に対応できる体制を整えましょう。
ステップ4:タイ側での輸入通関と決済の流れ
商品がタイに到着した後、現地の通関業者が通関を行います。このときライセンス・検査証明書・インボイス・パッキングリスト・B/L(船荷証券)などの提出が必要です。すべての情報が一致しているか、英語またはタイ語で明記されているかが審査のポイントになります。
通関後、商品は現地バイヤーや小売業者に引き渡され、あらかじめ取り決めた条件に基づき決済が行われます。銀行送金(TT)や信用状(L/C)などの支払方法も、この時点で重要な確認事項となります。スムーズな回収のため、決済条件は契約時に明確にしておくことが不可欠です。
タイ輸出で必要な書類一覧と作成のコツ
タイへ商品を輸出する際には通関や輸送、取引条件に応じたさまざまな書類の準備が必要です。ここでは代表的な書類であるインボイスやパッキングリストの基本、通関業者を活用する場合との違い、E-Customsにおける電子署名の扱い、そしてビザの必要性について解説します。
インボイス・パッキングリストの書き方
インボイス(商業送り状)は、商品内容や価格、取引条件を記載した輸出の基本書類です。金額の記載ミスや通貨単位の表記違いなどがあると、税関での審査が滞る可能性があります。以下の情報を含めて作成しましょう。
- 輸出者と輸入者の情報(会社名・住所)
- 商品名、数量、単価、合計金額
- 通貨(THB, JPY, USDなど)
- インコタームズ(FOB、CIFなど)と支払い条件
- 発送日・積地港・到着港
- シッピングマークまたはケースマーク
パッキングリストでは梱包単位やサイズ・重量などを記載します。複数商品を混載する場合は、個々の箱ごとの内容が明確であることが重要です。
またタイに輸出する際はシッピングマークまたはケースマークを製品に貼っておく必要があります。こちらがないことでタイ側が輸入できないこともありますので気を付けましょう。
自社対応・通関業者依頼時の必要書類の違い
通関業務を自社で行う場合と通関業者(フォワーダーなど)に依頼する場合では、求められる書類や準備負担が異なります。
【自社で対応する場合】
- インボイス、パッキングリスト、B/L(船荷証券)などを自ら整備
- 輸出申告書や各種検査証明も自社責任
- E-Customs操作や現地通関のやり取りが必要
【通関業者に依頼する場合】
- 基本的な書類の提出のみでOK
- 通関申請やE-Customs対応は代行される
- 指示や最終確認は必要なのでコミュニケーションが重要
初心者の場合は、まずは信頼できる業者に任せるのが安全です。
E-Customsでの電子署名・アクセス制限設定の注意点
- 登録時は会社代表者名義の電子証明書が必要
- 有効期限があるため、更新管理が必要
- 権限設定で誤って社外にアクセスを許可しないよう注意
- 担当者交代時には情報の更新・抹消が必要
タイ語でのやり取りが必要になるため、現地対応の経験がない場合は専門業者のサポートが不可欠です。
日本・タイ双方の規制と関税ルールを押さえる
タイへの輸出を成功させるためには、輸出国である日本と輸入国であるタイそれぞれの法規制や関税制度を正しく理解しておきましょう。ここでは日本からの輸出に関する規制、タイ側の輸入制限、品目ごとの検疫や関税の考え方について、実務経験に基づいて詳しく解説します。
日本からの輸出規制(物品・技術)とは?
日本から海外へ物品や技術を輸出する際には「外国為替及び外国貿易法(外為法)」による規制が適用されます。以下のようなものが規制対象となります。
- 軍事転用の可能性がある製品(デュアルユース品)
- 特定の技術・機械・装置などの高性能機器
- 一部の化学品・電子部品・光学機器
経済産業省の「リスト規制」や「キャッチオール規制」に該当する可能性があり、事前に輸出許可申請が必要になります。技術提供を含む場合は、物理的な輸送がなくても「みなし輸出」として取り扱われる点に注意が必要です。
タイ側の輸入規制・ライセンス制度の概要
タイでは輸入品に対して独自の規制や承認制度が設けられています。品目によっては関係省庁(保健省・工業省・農業省など)からの事前許可や登録が必要です。
禁制品・輸入制限品の代表例
タイでは以下のような品目が輸入禁止または制限対象となります。
区分主な品目規制内容禁制品麻薬類、わいせつ物、偽造品など完全輸入禁止管理品目化粧品、医療機器、電気製品、酒類など関係省庁の輸入許可が必要税関審査強化品中古品、精密機器など書類審査・実地検査が強化される傾向あり
該当する場合は「輸入ライセンス」の取得や製品登録が必要であり、手続きが煩雑な場合は現地通関業者との連携が欠かせません。タイではよく屋台でわいせつ物を売っている屋台が摘発されています。仏教国なので性的なものには厳しいです。
青果物・水産物の輸入条件と検疫手続き
青果物や水産物を輸出する場合には、タイ側の植物検疫・動物検疫の要件を満たす必要があります。食品や農産物は衛生・安全面での基準が厳しく、以下のような条件があります。
植物検疫・残留農薬・衛生管理のチェックポイント
- 農林水産省や保健省への事前登録・申請が必要な場合あり
- 残留農薬や添加物の基準値を超えると輸入不可
- 選果場・加工施設に対する登録要件(GAP/HACCP)
- タイ語でのラベル表示義務(原産地、成分、賞味期限等)
青果物は「輸入ごとに申告・検査」が求められる場合もあり、輸送スケジュールへの影響も考慮して手配することが重要です。
関税がかかる商品とかからない商品を見極める方法
タイは日本とEPA(経済連携協定)を締結しており、対象品目については関税が減免または撤廃されています。免税対象となるには「原産地証明書(Form JTEPA)」の提出が必要です。
関税の有無は、以下の点を確認することで判断できます。
- HSコードに基づく関税率表(タイ関税局HPなど)
- FTA/EPAの適用可否
- 原産地証明の有無と形式(電子・紙媒体)
税関での査定次第で課税対象になるケースもあるため、通関業者やフォワーダーと事前に相談しておくことがリスク回避になります。関税を正しく理解することは価格競争力を保ちながら現地市場にスムーズに参入するために大切です。私も商社時代に関税の確認を怠り、300万円以上の損害を出しました。笑
よくある失敗と課題を事前に知って回避しよう
初めて輸出に取り組む中小企業にとって書類不備や物流コスト、現地との意思疎通のギャップは代表的な課題です。ここでは現場で実際に起きやすい失敗と、その回避策について解説します。
通関トラブル(ラベル不備・書類ミス)
もっとも頻繁に見られるのが、通関時の書類不備やラベル表記のミスです。「成分表示の不備」「商品の原産地の記載漏れ」「タイ語ラベルが未対応」などがあると、税関で止められ、追加検査や再提出が必要になります。対策としては以下のような準備が有効です。
- 出荷前にすべての書類(インボイス・パッキングリスト・ライセンス等)を第三者とWチェック
- ラベルはタイ語表記が必要かを確認し、必要であれば翻訳・印刷対応
- 通関業者と事前に書類の雛形や注意点を共有しておく
輸送・物流費用の高騰対策
近年は原油価格や世界的な物流混乱の影響で、輸送費が高騰傾向にあります。LCL(小口混載)や航空便を多用する場合、1件あたりのコストが大きくなりがちです。
- シーズンや燃油サーチャージを見越してスケジュール調整
- 船便を活用したコンテナ輸送(FCL)に切り替え
- 複数のフォワーダーから見積もりを取得し、条件を比較検討
- EC販売などでは、タイ国内物流パートナーと連携し、倉庫保管+小口配送の導入
現地とのコミュニケーションギャップによる商談失敗
言語の壁や商習慣の違いによって、誤解や期待のズレが生じることも珍しくありません。日本では当たり前の納期厳守が、タイでは「多少の遅れは想定内」と認識されているケースもあります。
- 契約書や見積書に詳細な条件(納期・数量・品質基準)を明記
- 商談やフォローアップで通訳を介し、意図を丁寧に伝える
- 定期的な連絡と報告を行い、信頼関係を築く
事前の準備と丁寧な対応が失敗を未然に防ぎ、安定した取引関係の構築につながります。
輸出初心者・人手不足の企業が利用すべき支援とは?
「書類の作成方法がわからない」「タイ語対応ができない」「現地バイヤーへの営業が難しい」といった課題を抱える企業は多く存在します。ここでは、そうした課題を乗り越えるために利用できる支援サービスについて、公的機関と実務型民間支援の両面からご紹介します。
JETROなどの公的支援とその限界
海外展開支援といえば、まず思い浮かぶのがJETRO(日本貿易振興機構)です。タイ市場に関しても展示会出展支援、市場情報の提供、マッチングイベントの実施など、多くの支援メニューがあります。しかしながら、以下のような課題を感じる企業も少なくありません。
- 実務面のサポート(通関・物流・交渉など)は対象外
- 支援期間が短期で、フォローアップが弱い
- 各種手続きや相談は英語・日本語対応が中心で、タイ語対応が限定的
そのため、実際の現場対応や継続的な営業活動には、民間による実行支援の併用が効果的です。
実行型の伴走サポート「丸投げ貿易」の特徴
「丸投げ貿易」は、タイ市場に特化した中小企業向けの輸出支援サービスです。依頼者は18年間のタイ在住歴とタイ支店で13年間海外営業を経験。通関、物流、商談、販路開拓に至るまで、机上ではない実務型支援を一貫して提供しています。
書類作成・通関・物流まで丸ごと対応
- インボイス・パッキングリストの作成支援
- 通関業者との調整やHSコード選定
- タイ語対応の物流会社選定とリードタイム管理
- 化粧品・雑貨・食品等カテゴリ別の通関アドバイス
現地バイヤー営業・商談通訳・EC出品代行も可能
- タイ語・英語での営業メール代行(業種・地域別ターゲティング)
- オンライン商談の同席および通訳支援(日本語⇔タイ語)
- Shopee・Lazada等ECモールへの出品支援(SEO設計含む)
- 商談内容のレポート化+継続アプローチのアドバイス
SNSやLP制作による販促支援で売れる仕組みを構築
- タイ語SNS(Instagram・LINE公式)運用の代行支援
- 商品紹介LPの構成・翻訳・コピーライティング支援
- 現地の文化・表現に合わせたプロモーション企画と画像制作
タイ語ネイティブとの連携体制や、現地企業ネットワークも活用しながら、「成果につながる支援」を重視しています。「自社だけでは対応できない」と感じた時こそ、こうした実務型パートナーの活用を検討してみてください。
タイ輸出はやり方さえ掴めば難しくない
タイへの輸出には、規制や書類、現地対応などの壁があるのは事実ですが、それらを正しく理解し、専門家と連携すれば決して難しいものではありません。
ポイントは「最初の流れを正確に掴むこと」と「実行経験のあるパートナーに頼ること」です。
実務を熟知した支援者の存在があるだけで、不安や負担を大幅に軽減できます。
タイ語・通関・物流・商談すべてに対応できる「丸投げ貿易」では、煩雑な手続きを一括でサポート。書類作成から現地営業、販路開拓までワンストップで任せられるため、スピーディーかつ確実に輸出を始めたい企業に最適です。
はじめの一歩を迷わず踏み出したい方は、ぜひご相談ください。
こちらもおすすめ





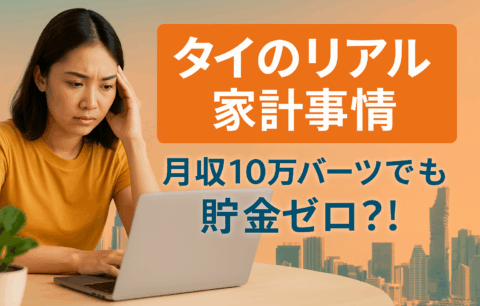
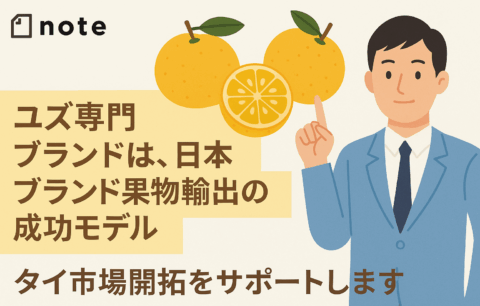
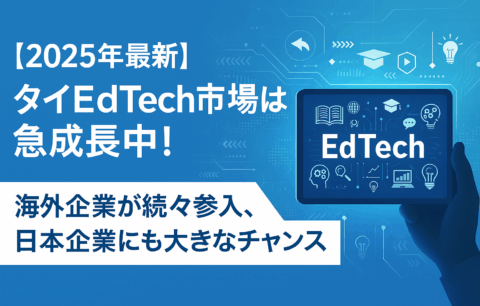

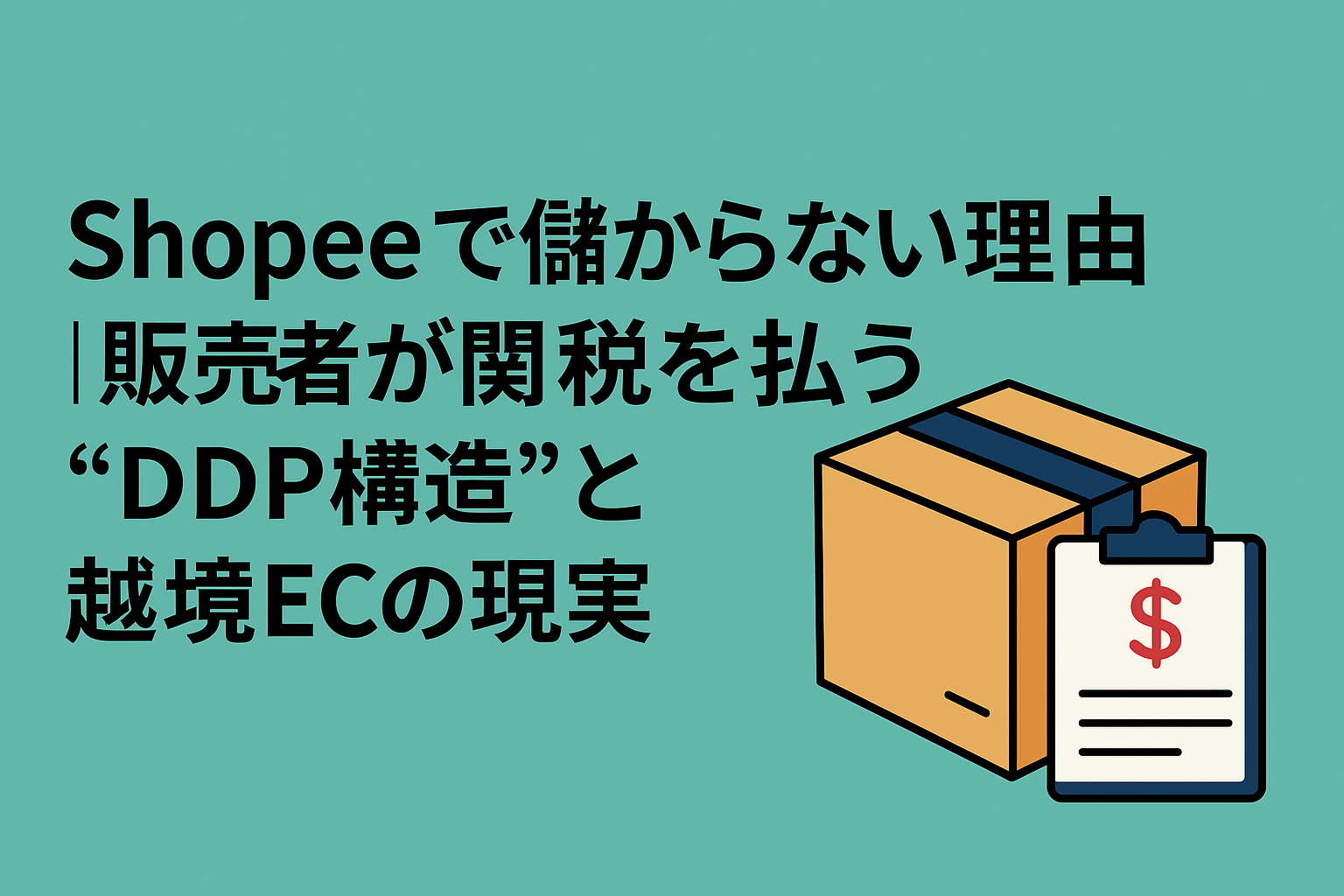

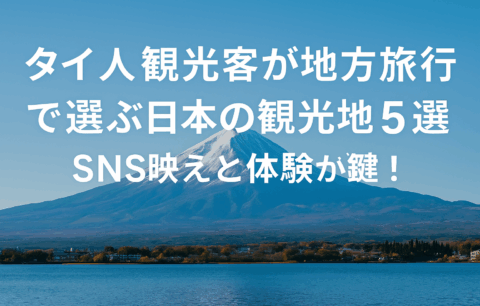


コメント